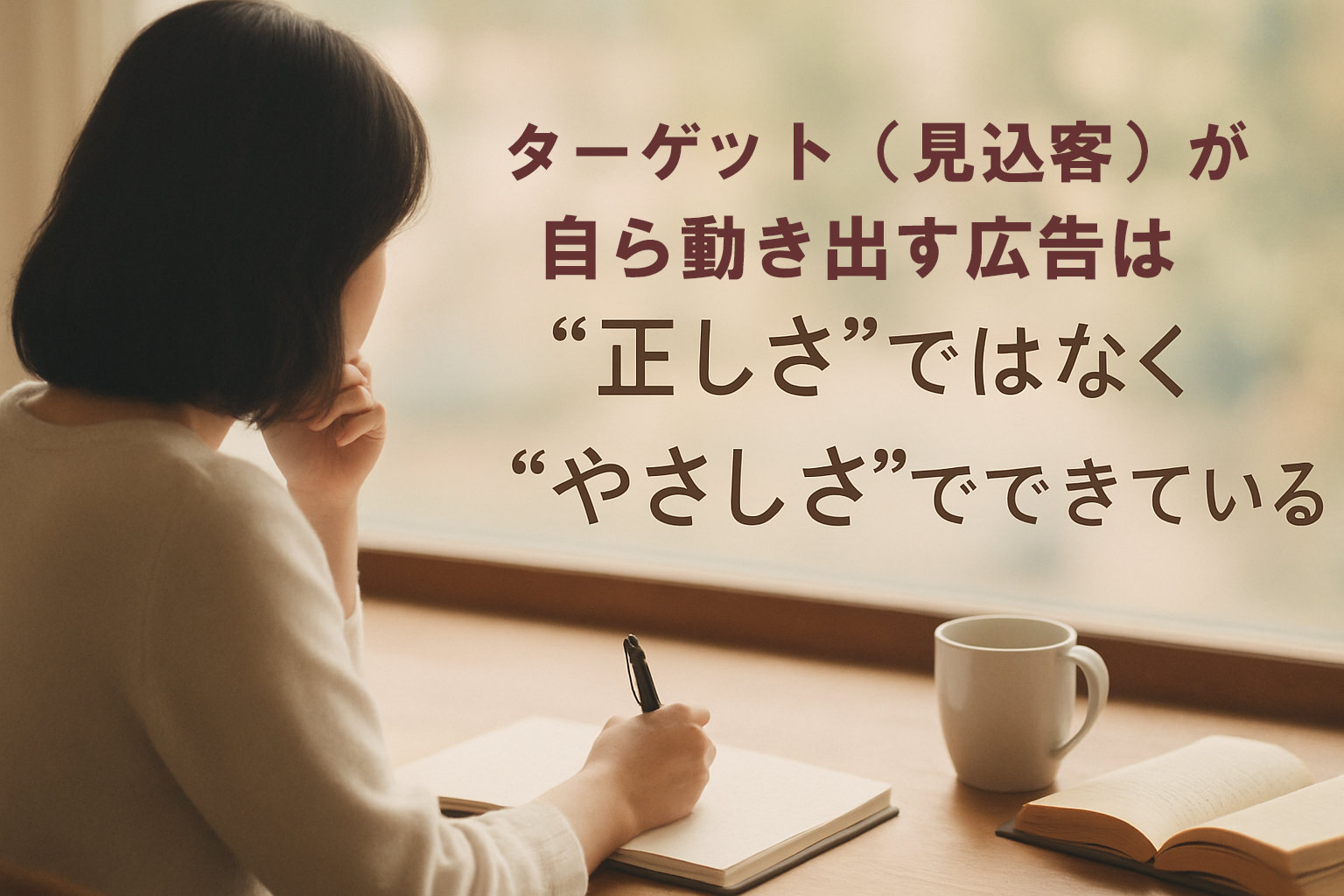「広告を出しても、反応がない…」
これは、
多くのビジネスオーナーが一度は感じたことがある悩みです。
広告を一生懸命作っても、売れない。
時間をかけて作ったランディングページも、
思ったほど申込が来ない。
実はこれ、
「商品が悪いから」
ではないことがほとんどです。
問題は、
読者の感情の流れを“設計”していないこと。
広告には、
必ず超えるべき「3つの壁」があります。
1つ目は「興味がない(無関心)」、
2つ目は「本当かな?(疑念)」、
3つ目は「面倒だな、後でいいや(抵抗感)」。
この3つを突破するための方法として、
どうやって広告の冒頭で興味を引くか
-
どうやって疑念を取り除くか
-
どうやって今すぐ動いてもらうか
-
そして、どうやって記憶に残る“締め”にするか
まず、
ユーザー目線で考えてみましょう。
多くの人は、
自分が抱えている問題に気づいていないことがあります。
だからこそ、
広告ではまず
「日常の何気ない場面」や
「誰もが経験しそうな具体例」を使って、
「これ、自分のことかも」と自然に共感してもらうことが大切です。
このときに絶対にやってはいけないのが、
読者を責めることです。
「あなたが悪い」
「こんなこともできないの?」
と感じさせてしまうと、
心を閉ざされてしまいます。
そこで必要なのが、
「本当の悪者(原因)はここにある」
と優しく示すこと。
たとえば、
「あなたが疲れているのは、意志が弱いからではありません。
その原因は、仕組みが非効率だったりサポートがなかったからなんです」
というように、
問題を読者の外側に置くことで、
安心して読み進めてもらえます。
そして次に、
「その悩みをどうすれば解決できるのか?」
という道筋を具体的に提示します。
このとき、
商品やサービスは売り込むのではなく、
「一緒にその問題を解決する味方」
として紹介するのがポイントです。
読者に
「もしこの問題が解決できたら、どんな日々が待っているのか?」
を想像させましょう。
理想の未来が、
ただの夢物語ではなく
「自分にも手が届く」
と思えるようなリアルな描写で伝えると、
読者の心は自然と動き出します。
この一連の流れ――
-
気づいていない問題に具体例で気づかせる
-
読者を責めず、外的な原因を示す
-
その解決策として商品を“味方”として提案する
-
解決後の未来をリアルに想像させる
――これが、
どんな業種や商品にも使える
「心を動かす広告ストーリーの基本構造」
です。
これらを10のステップで丁寧に解説し、
ご用意しました。
ぜひ、あなたの広告に当てはめて応用してみてください。
広告を
「売るための文書」
から、
「人を動かす物語」
へ変えたいなら、
きっとこのテンプレートは、
あなたの武器になります。
あなたの商品にも物語の力を宿してください。
- なぜ広告は“届かない”のか?──見えない3つの壁とは
- 関心を持ってもらえなければ、すべては始まらない
- あなたは信じられる人なのか?
- なぜ人は“行動”を先延ばしにするのか?
- 広告が物語になると、人は夢中になる
- 主人公=お客様。敵役を見せよ!
- 共感されるブランドは“助ける存在”である
- 証拠が弱い広告は、心に刺さらない
- 期限と行動を提示せよ
- 行動を“物語の結末”にせよ
- 【具体的な応用例】
- 教育・講座系(オンライン講座、資格取得、個別学習サポートなど)
- 恋愛・占い・自己啓発系(恋愛講座、スピリチュアル鑑定、メンタルサポート、カウンセリング等)
- 不動産・暮らし・家系(空き家管理、賃貸管理、リフォーム、片付け、ライフサポートなど)
- 士業・代行・BtoB系(行政書士、税理士、代行業、業務コンサル、業務委託など)
- ファッション・ジュエリー・装飾品(服、アクセサリー、靴、バッグ、時計、帽子など)
- IT・Web・ツール系(業務効率化ツール、アプリ、SaaS、Webサービス、クラウドサービスなど)
- 趣味・体験・レジャー系(習い事、ワークショップ、旅行、アウトドア体験、非日常サービスなど)
なぜ広告は“届かない”のか?──見えない3つの壁とは
あなたがどれほど素晴らしい商品やサービスを提供していても、それを知ってもらえなければ意味がない。ましてや、知ってもらうだけでは足りない。人が「行動」を起こすには、乗り越えるべき“3つの壁”がある。しかもその壁は、目に見えない。そして厄介なことに、多くの広告がこの壁の存在に気づかないまま、大切な予算と時間を浪費しているのだ。
広告の三重苦:無関心・疑念・抵抗感
人が広告を見たとき、
まず第一に抱く感情は「興味がない」という感情、
すなわち【無関心】である。
次に、「本当か?」という【疑念】が湧き、
最後に「なんとなく怪しい」「今は面倒」
といった【抵抗感】が芽生える。
これらの感情は、自然な心理反応であり、広告主が悪いわけではない。
むしろ、広告を見る側にとっては“防衛本能”ともいえる。
ネット上には無数の広告が溢れ、
詐欺まがいの情報も跋扈する現代、
誰もが「だまされないように」
と無意識に壁を築いているのだ。
それでは、それぞれの壁についてもう少し具体的に見ていこう。
【第1の壁】無関心 ──「知らないし、興味もない」
世の中の99.9%の人は、
あなたの商品やサービスに興味を持っていない。
残酷だが、それが現実だ。
自分ごととして認識されなければ、
どれほど熱意を込めて作られた広告であっても、
目にも留まらない。
テレビで流れるCMの8割が頭に残らないのと同じように、
人は自分に関係ないと判断した瞬間に“情報を遮断”する。
つまり、最初に超えなければならないのは、
「どうでもいい」と思われる状態。
目を留めてもらい、
「あれ?これ、自分に関係あるかも」
と思わせる工夫がなければ、
話は一歩も前に進まない。
【第2の壁】疑念 ──「本当なの?どうせ盛ってるんでしょ?」
次に訪れるのが
「それ、本当に信じていいの?」
という【疑念】の壁だ。
現代のユーザーは広告的な表現に対して、非常に敏感だ。
あまりにも良い話、あまりにも派手な成果、
あまりにも都合の良いストーリーは、
「どうせ嘘でしょ」
「盛ってるだけでしょ」
と疑われる。
情報が氾濫する現代、
消費者は賢くなった。
口コミ、SNS、レビューをすぐに調べる。
だからこそ、広告では「誠実さ」と「根拠」が求められる。
証拠のない成功談や、
裏付けのない主張は、
信じてもらえないどころか、
逆効果になる。
【第3の壁】抵抗感 ──「気になるけど…今じゃなくていいや」
最後に立ちはだかるのが、【抵抗感】という壁だ。
これは非常に見えにくく、強力な敵である。
例えば、
「良さそうだな」と思っても、
「今は忙しいから」
「また後で読もう」
と先延ばしされる。
興味はあるけど、
行動にまでは至らない。
ここで多くの広告は、
最終的な
「申し込み」
「購入」
まで至らずに終わってしまう。
この壁を超えるには、
今この瞬間に動く理由を提示する必要がある。
期限付きの特典、
数量限定の案内、
機会損失の明示
──これらはすべて、
「行動を促す仕掛け」であり、
この第三の壁を崩すための必須要素なのだ。
広告は、感情の流れを設計する“装置”
ここまで読んできたあなたは、すでに気づいているかもしれない。
広告とは、
ただ情報を伝えるものではない。
感情を動かし、行動を生むための装置である。
そしてその装置がうまく作動するには、
これら3つの壁を順番に、
段階的に乗り越える必要がある。
「広告の3つの壁」
-
無関心を突破して、目を留めさせる
-
疑念を払拭して、信じてもらう
-
抵抗感を打ち消して、動いてもらう
この順番を無視して、
「いますぐ買ってください!」
と叫ぶ広告がいかに多いことか。
そして、いかにスルーされ、
嫌われ、記憶に残らず消えていくことか──。
広告は、見えない壁を突破する“物語”である
では、どうやってこの3つの壁を超えるのか?
そのヒントが「ストーリーブランド戦略」にある。
商品を売るのではなく、
顧客の物語の中で、問題を解決する武器として商品を登場させる。
広告とは、
感情を揺さぶり、
行動を促す物語でなければならない。
次回はその「第1の壁・無関心」をどう突破するのか?
──印象的な導入で自分ごと化させる
ストーリーテクニックを深掘りしていこう。
関心を持ってもらえなければ、すべては始まらない
──第一の壁「無関心」に打ち勝つ“自分ごと化”の技術
「興味がない」
──これは広告にとって、最大の敵である。
優れた商品、
緻密に計算されたLP、
美しいデザインや写真。
それらすべてが完璧だったとしても、
最初の1秒でスルーされてしまえば意味はない。
だからこそ、
広告の第一歩である「無関心の壁」を突破できるかどうかが、
すべてを決める。
なぜ人は“無関心”なのか?
人は本能的に、自分に関係ない情報を切り捨てる。
スマホを開けば、
広告・SNS・通知・バナー・メール…
ありとあらゆる「呼びかけ」が飛び込んでくる中、
人はどうやって必要な情報だけを選別しているのか?
それが「自分に関係あるかどうか」の判断だ。
つまり、
自分に関係ないと0.5秒で感じられた情報は、
見られる前に捨てられている。
ここが非常に恐ろしい。
あなたの広告が「読まれない」のではなく、
「読まれる前に除外されている」可能性が高いのだ。
解決法は「自分ごと化」──主役を取り戻せ
広告を読んでもらうためには、
まず相手に「これは自分のことだ」と思わせる必要がある。
これを「自分ごと化」という。
よくある失敗例は、
「売り手目線の主張」ばかりが先に立ってしまい、
読み手との接点がないこと。
例えば、
次のようなコピーはどうだろうか?
最高品質の天然成分を使用した、エビデンスに基づくサプリメントを今だけ50%オフ!
…これでは「ふーん」で終わってしまう。
どれだけ優れていても、
「自分には関係ない」
と思われた瞬間に終わりだ。
では、こう書いたらどうだろうか?
朝スッキリ起きられないあなたへ──
「やる気が出ない日々」が、嘘のように変わったある習慣とは?
同じ商品でも、
「読み手の悩み」から始めると、
まるで違う。
「あ、これ、自分のことかも」と思わせた時点で、
興味の扉は開かれる。
「刺さる見出し」の正体とは?
見出しは、
広告における入り口だ。
その一文だけで、
「読む or 読まない」
が決まる。
よくコピーライターたちは「見出しが8割」と言う。
なぜなら、
見出しで引っかからなければ、
本文は永遠に読まれないからだ。
効果的な見出しの要素:
-
読者の悩みを代弁する
-
意外性・矛盾・驚きを含む
-
ベネフィットが一目でわかる
-
時間・限定・緊急性の提示
-
質問形で好奇心を刺激する
例:
-
「なぜ“やる気が出ない”のか?その原因は朝の〇〇だった」
-
「副業がうまくいかない人が“絶対にやっていない”たった1つのこと」
-
「失敗しないダイエット、たった3つのルールとは?」
ここでは言葉選びが非常に重要だ。
「無料」
「限定」
「まだ間に合う」
「◯%が知らない」
といった言葉には、
特に反応が起こりやすい。
「あるある」を使え、共感こそ最強の引き金
人が最も反応しやすいのは、
自分が体験したことに似たストーリーだ。
たとえば、
「朝起きられない」
「人間関係が面倒」
「副業を始めたが稼げない」
「食事制限が続かない」
──こうしたあるあるが見出しや冒頭にあれば、
無関心の壁は少しずつ崩れはじめる。
つまり、
読者が自分のことを語られていると錯覚する広告こそ、
無関心の壁を突破できる。
「物語」の導入に“問題提起”を仕込め
ストーリーブランド戦略では、
常に「問題」が物語の出発点になる。
広告でも同じことが言える。
見出しで注目を引いたら、
次にやるべきは「読者が直面している問題を明らかにする」ことだ。
ここでのポイントは、
問題を気づかせること。
多くの人は、自分の本当の悩みに気づいていないことが多い。
例:
-
なんとなくやる気が出ない
→ 原因は腸内環境の乱れかも -
集中力が続かない
→ 実は睡眠リズムがズレている -
売上が伸びない
→ お客さんの“言葉”を使っていないからかも
広告の中で
「え、それが原因だったの?」
と感じてもらえたら、
それだけで続きを読まずにはいられない状態を作り出せる。
無関心の壁を突破する3ステップ
-
読者の悩みをズバリ言い当てる(共感)
-
「実はそれ、〇〇が原因かも」と気づかせる(問題提起)
-
「続きが知りたい」と思わせる(好奇心の喚起)
この3つのステップを広告の冒頭に組み込むだけで、
読まれる確率は劇的に上がる。
広告の入口は「自分のことだ」と思わせること
人は、自分の人生に関係ないものには反応しない。
つまり、
広告とは
「読者に自分のこととして受け取らせる技術」
でもある。
無関心の壁を突破するために必要なのは、
商品の魅力ではない。
読者が自分の課題として感じるテーマを提示し、
問題に気づかせることだ。
読まれる広告とは、
読者が「自分のことを理解してくれている」
と感じる広告である。
次回は、「そうは言っても本当か?」という読者の疑念を打ち砕く、
信頼の設計について掘り下げていく。
あなたは信じられる人なのか?
──第二の壁「疑念」を越える信頼の構築法
無関心の壁を越え、
ようやく相手が広告を読み始めてくれた。
ここで多くの広告主がホッとするが、
油断してはいけない。
その先に待っているのは、
第二の壁――「疑念」だ。
広告を読む人は、
内心こう思っている。
「本当にこの商品、効果あるの?」
「大げさに言ってるだけじゃない?」
「なんかうさんくさい…」
これは、
現代の情報過多社会で身につけた防御本能だ。
詐欺的広告、
やらせレビュー、
インフルエンサーの提灯投稿…。
人々はもはや、
「本当のこと」しか信じない。
だからこそ、あなたの広告は、
「疑念を持つことが前提の世界」
で戦う覚悟が必要になる。
「疑われるのが当然」という前提に立つ
まず大事なのは、
読者は最初からあなたを疑っているという前提を持つこと。
広告主としては、
実績もこだわりも自信もある。
けれど、
広告を読む相手は、
それを何も知らない状態だ。
信用の“し”の字もない段階からスタートしている。
つまり、
あなたの広告が伝えるメッセージのすべては、
「証明されるべき仮説」として見られている。
これを理解していない広告は、
たちまち見透かされてしまう。
疑念の壁を崩す5つの“信頼設計”
読者の心に生まれる疑念を取り除くには、
次の5つの要素を意識するとよい。
1. 実績の提示(数値化された結果)
→ どれだけの人が効果を実感しているのか?
→ 何年の運用実績があるのか?
→ 累計販売数やリピート率は?
数字があるだけで、
言葉の信ぴょう性は一気に高まる。
例:
-
累計販売10万本突破
-
3か月以内のリピート率87%
-
楽天レビュー平均★4.8(5点満点)
数は、感情に勝る。
2. 具体的なストーリー
→ 抽象的な“成功体験”では疑われる。
→ 具体的な「背景→行動→結果」のストーリーが信頼を生む。
NG例:「これを飲んで人生が変わりました」
OK例:「産後太りに悩んでいた主婦が、3ヶ月で−8kg。ジムにも行かず、食事制限もなし。1日1回飲むだけの習慣が、気づけば体質を変えていた。」
人はストーリーにリアリティを感じると納得する。
3. 第三者の声(口コミ・レビュー・SNS投稿)
→ 第三者の証言は、自己主張より100倍信じられる。
Amazonのレビュー、
SNSの口コミ、
取材記事などは、
「中立的な立場」
の声として読者の疑念を和らげる。
ポイント:
-
数が多いほど信頼度が増す
-
ネガティブな意見も混ざっている方がリアル
-
一般人の生々しい投稿が特に強い
4. ビフォーアフターの視覚情報
→ 疑念を打ち砕く最強の武器は、「目に見える変化」
画像・動画・比較表などで
「変化」
が視覚的に伝わると、
「本当に効果あるんだ」
と思わせることができる。
ただし、
加工感のある写真や演出が強すぎると逆効果になる。
リアル感が命。
「素人っぽさ」
がむしろ武器になる。
5. 保証・返金制度の提示
→ 最終的な疑念は「損したくない」という不安
その壁を取り除くには、
「失敗してもリスクがない」
と思わせること。
例:
-
全額返金保証(〇日間)
-
初回購入者限定・30日以内返品可能
-
定期縛りなし、1回だけでもOK
安心して試せる環境を提供することで、
疑念の最後のとげを抜くことができる。
信頼は積み重ねるものであり、積極的に設計すべきものである
広告の世界では、
信頼は自然には生まれない。
明確に、
意図して、
設計しなければならない。
「良い商品なら売れる」は幻想だ。
良い商品を、
「良いと感じてもらえるように伝える力」
が必要なのだ。
あなたが売っているのは商品ではない。
それによって得られる未来であり、
それを信じてもらうための証拠の積み重ねである。
疑念は“情報”と“証拠”で消せ
-
人は、無意識に広告を疑う
-
信頼は、証拠によってしか築けない
-
「第三者の声」と「具体性」が信頼を生む
-
安心して試せる環境をつくることで、最後の抵抗を消す
無関心の壁を越えたら、
すぐに疑念という次の壁が現れる。
この壁を乗り越えるには、
「信頼という階段」
を一歩ずつ設計するしかない。
次回は、その先にある最後の壁──
「わかるけど、面倒」
「やりたいけど、あとでいい」
という
【抵抗感】
の正体と崩し方について、
さらに深く掘り下げていく。
なぜ人は“行動”を先延ばしにするのか?
──第三の壁「抵抗感」が生まれる心理的メカニズムと突破法
あなたの広告は、
「興味がない」という第一の壁を突破し、
「本当か?」という第二の疑念も乗り越えた。
読者は商品に興味を持ち、
内容を理解し、
信頼し始めている――
それでも、
なぜ“購入”や“申し込み”という行動に至らないのか?
その理由は、
最後に立ちはだかる第三の壁、
「抵抗感(心理的ブレーキ)」
である。
抵抗感とは、“理屈”ではなく“感情”が生む壁
興味もあるし、
信頼もしている――
でも、
なぜか
「あとでいいや」
と思ってしまう。
「気になるけど、別に急がないし」
とスルーしてしまう。
この感情の停滞こそが、第三の壁だ。
そしてこの壁の正体は、
「変化」への不安であり、
「行動」へのエネルギー消費
への抵抗である。
人は本能的に
「現状維持」
を選びたがる生き物だ。
行動を起こすことには、
常に「リスク」や「面倒」がつきまとう。
だから、
頭では理解していても、行動しない
という現象が起こるのだ。
抵抗感が生まれる5つの原因
1. 「今じゃなくていい」という先延ばしグセ
→ 多くの人は、重要なことより目先の快を優先する。
「興味はあるけど、今やらなくても大丈夫」
と思ってしまうのは、
人間の習性。
2. 「難しそう」という操作や手続きへの不安
→ フォームが複雑、
決済方法がわかりづらい、
特典の受け取り方が不明瞭…
ちょっとした手間が「面倒くさい」という感情を呼び、
即離脱につながる。
3. 「失敗したくない」というリスク回避思考
→ 「お金を払って損をしたらどうしよう」
「効果がなかったらイヤだ」
という未来への不安。
4. 「誰かに相談したい」という決定権の保留
→ 特に高額商品や長期契約は、
パートナーや上司に相談する心理が働きやすい。
5. 「信用はしてるけど、一歩が踏み出せない」
→ これは“感情”の問題。
どれだけ情報や証拠が揃っていても、
最後は気分が後押ししなければ人は動かない。
抵抗感を打ち破る「3つの仕掛け」
1. 緊急性の演出
→ 「今じゃなきゃダメだ」と思わせる状況をつくる。
有効な切り口:
-
限定数(残り7名/あと3本)
-
締切(本日23:59まで)
-
限定特典(先着○名のみ)
人は「選択肢が減る」ことを嫌う。
その心理を利用して、「今動かないと損」と思わせる。
2. 行動のハードルを下げる
→ 迷わず・悩まず・すぐにできるようにする。
チェックポイント:
-
フォームは最短・簡潔に
-
決済や申し込み方法を1ステップで完了できる設計に
-
「今すぐ使える!」をイメージさせる導線設計
例:
「たった60秒で登録完了」
「今すぐこのボタンを押すだけでOK」
「LINE登録するだけで無料プレゼントGET」
3. 後押しの一言を入れる(感情の背中押し)
→ 最後に必要なのは理屈ではなく言葉だ。
例:
-
「迷っているなら、まず試してみてください。」
-
「1回だけの行動が、人生を変えるかもしれません。」
-
「あなたのような方にこそ、これを届けたいと思っています。」
人の背中を押すのは、
最後は共感と想い。
“自分のために言ってくれてる”という感覚
があると、感情が動く。
ストーリーの中でも、抵抗感は“クライマックス”で発生する
映画でも小説でも、
主人公は最後の決断を前に葛藤する。
ヒーローが敵に立ち向かうかどうか、
旅に出るかどうか、
愛を告白するかどうか…。
読者や観客は、
その“一歩を踏み出す瞬間”に強く感情移入する。
広告も同じだ。
読者の気持ちが
「動こうか、どうしようか」
と揺れているそのとき、
あなたの言葉がその背中を押せるかどうかが、運命を決める。
実例:抵抗感を突破したLP構成の一部
-
共感を生む悩み提起
-
原因の気づき
-
解決策の提示
-
証拠と実績
-
安心設計(返金保証など)
-
緊急性と限定性
-
明快なCTA(今すぐ申し込む)
-
最後の一言:「迷うなら、まずは試してみてください。」
この8ステップの構成で、
「知る→信じる→動く」
という行動の連鎖をつくり、
無関心 → 疑念 → 抵抗感という3つの壁を乗り越えていく。
「感情を動かせば、行動は生まれる」
-
抵抗感は理屈ではなく“感情”の壁
-
急がないと損する状況を演出する
-
手間と不安を徹底的に取り除く
-
最後に“背中を押す言葉”が人を動かす
読者が行動を起こすには、
「情報」よりも
「タイミング」と「気持ち」
が重要だ。
あなたの広告が
今、ここで動く意味をしっかりと伝えられれば、
抵抗感は静かに、
そして確実に崩れていく。
次回は、いよいよこの3つの壁を突破するための
「物語設計」
の実践編。
読者を主人公にし、
商品を“武器”として登場させるストーリーブランディング
の核心に迫ります。
広告が物語になると、人は夢中になる
──なぜストーリーは人の心に響くのか?脳科学とマーケの交差点
広告は本来、
売るための手段だ。
けれど、
「売ろう」
という姿勢が見える広告ほど、
なぜか人は引いてしまう。
一方、
物語の中にスッと入り込み、
気づけば商品やサービスに興味を持ち、
最後には
「なんだかこれ、欲しいかも」
と思ってしまう──
そんな広告がある。
そしてその広告は、例外なく
「ストーリー」
を使っている。
なぜストーリーは、
広告に強い力を与えるのか?
その秘密は、
脳の仕組みと人間の本能
に隠されている。
人の脳は「物語」によって動かされる
脳科学の世界では、
こんな実験結果がある。
事実だけを並べた文章を読んだとき、脳は「言語野」だけを使って処理する。
一方、物語として語られた内容を読んだときは、「視覚野」「運動野」「感情野」など複数の部位が活性化する。
つまり、
人はストーリーに触れると、頭の中で「擬似体験」しているのだ。
たとえば、
-
誰かが高熱を出して苦しんでいるシーンを読むと、
読者の身体にも熱を感じるような反応が起きる。 -
主人公が心臓をドキドキさせる場面では、
読者の心拍数も上がることがある。
これは
「ミラーニューロン」
と呼ばれる神経細胞の働きによるもの。
人間は、
物語を通じて他人の体験を自分のことのように感じる能力を持っている。
だからこそ、
ストーリーには「人の感情を動かす力」がある。
広告に必要なのは、商品紹介ではなく「物語の演出」
では、
このストーリーの力を広告にどう生かすのか?
それは、
広告を
「売り手の語り」ではなく
「読者の物語」として設計することだ。
広告でやるべきことは、
商品を売り込むことではない。
読者を主人公にして、
問題を提示し、
解決への道を描くことだ。
そして、
あなたの商品やサービスは、
「その道中で出会う強力な助っ人」
として登場すればいい。
ストーリーブランド戦略の核心:あなたの商品は“武器”である
『ストーリーブランド戦略』(ドナルド・ミラー著)では、
広告におけるブランドの役割をこう定義している。
あなた(ブランド)は主人公ではない。
主人公は顧客であり、
あなたは“ガイド役”であり、
あなたの商品は“悪と戦うための武器”である。
これは非常に重要な視点だ。
ほとんどの広告が失敗する理由は、
「私たちの商品はこんなにすごいですよ!」
と自分語りに終始しているから。
けれど、
人は他人の武勇伝には興味がない。
自分の問題を解決してくれるストーリーにしか反応しない。
ストーリー設計の基本構造(7つの要素)
ストーリーとして広告を設計する際には、
以下の7ステップが有効だ。
1. 主人公(=顧客)が
2. 問題に直面し
3. 解決のために“ガイド(=あなた)”と出会い
4. ガイドが“計画”を示し
5. 行動を促し
6. その結果として“成功”を手にし
7. “失敗”を回避する
この構成は、
ハリウッド映画のほとんどに使われている
「ヒーローズジャーニー」
にも通じている。
実例:ストーリーブランドを使ったLPの冒頭
【悪い例】
この商品は、最先端の技術を使った◯◯で、業界初の◯◯を実現し…
→ 典型的な「企業が主語」の広告。読者は置いてけぼり。
【良い例】
毎朝、鏡を見るたびにため息をついていた私。
「またシミが増えた…」「肌がくすんで見える…」
そんな自分を変えたくて、思い切って試したのが──
→ 「私(読者)」が主人公。問題が提示され、解決のストーリーが始まる。
この違いだけで、読み手の没入感は大きく変わる。
なぜ“悪役”が必要なのか?
ストーリーには必ず“敵”が必要だ。
ボーンにCIAの追手がいなければ、
ハリー・ポッターにヴォルデモートがいなければ、
バットマンにジョーカーがいなければ…
物語は“退屈”になる。
広告でも同じことが言える。
読者が直面する問題や不便、損失、怒り、恥ずかしさなどの
“悪役”を明確に描かなければ、
その商品が
「なぜ必要なのか」
が伝わらない。
敵が強大であればあるほど、あなたの商品(=武器)の価値は際立つ。
「感情→共感→行動」の3段階で人は動く
-
感情を刺激する(ストーリー)
-
共感させる(読者が主人公)
-
行動を導く(解決=商品)
これが、
ストーリーブランド広告の流れだ。
単に商品を紹介するのではなく、
読者の頭の中に「自分が主人公の物語」を描かせる。
その中に自然に商品を登場させる。
こうすることで、「買わせようとしている」という警戒心が消え、
人は自然とその世界に入り込む。
人は「売り込み」には反応しない。だが「物語」には夢中になる。
-
ストーリーは脳の深い部分を刺激し、感情と行動を引き出す
-
主人公はあなたではなく、顧客である
-
商品は「問題を解決するための武器」として登場させる
-
「問題 → 解決 → 成功」の流れを自然に描くことで、
違和感なく“買う理由”を与えられる
広告にストーリーを組み込むことで、
人は単なる“商品の紹介”ではなく、
“自分の人生の転機”として受け取るようになる。
そして、それこそが本当に人の心を動かす広告なのだ。
主人公=お客様。敵役を見せよ!
──問題を描くことで共感が生まれる理由
「人は問題がないと、物語に興味を持たない」
この事実は、
すべての広告制作者、
商品開発者、
起業家
にとって心に刻むべき核心だ。
ストーリーには必ず“敵”が登場する。
主人公はその敵を乗り越えることで成長し、
読者はその過程に没入する。
これは映画でも、
小説でも、
そして広告でも変わらない。
広告でいう敵とは、
お客様が直面している「問題」である。
商品やサービスの話をする前に、
「あなたにはこんな問題がありますよね」と代弁することができるかどうか――
そこに、
共感が生まれ、
興味が生まれ、
行動の芽が育つ。
問題のない物語に、人は共感しない
あなたがテレビをつけたとき、
「すべてが順調な主人公が、何も困らず、淡々と成功していくドラマ」
が流れていたとしたら、
最後まで見るだろうか?
きっと、
途中でチャンネルを変える。
なぜなら、
そこには“緊張”も“期待”も“共感”もないからだ。
人は、
誰かが問題に直面し、
それを乗り越えようとあがく姿に感情移入する。
「その気持ち、わかる」
「自分もそうだった」
と思えるからこそ、
物語に引き込まれる。
広告においてもまったく同じことが言える。
問題を描くとは、顧客の“心の中”を代弁すること
広告における問題とは、
単なる不便や課題ではない。
その人の感情を揺さぶっている「もやもや」のことだ。
例えば――
商品:腸内環境を整えるサプリ
× 機能だけ伝える広告:
「腸内フローラを整える、乳酸菌サプリです。」
○ 問題を描く広告:
「朝スッキリ起きられない。毎日だるい。食べてないのにお腹が張る。
それ、“腸のSOS”かもしれません。」
→ 読者の“日常的なストレス”を代弁し、「あ、それ自分かも」と思わせる。
このように、
顧客の“内面にある感情”を言語化できるかどうかが、
問題提起の成否を分ける。
問題を3層構造で考えると、より強く刺さる
問題には「3つの層」があると言われている。
-
外的問題:目に見える不便・障害
(例:髪が抜ける、肩がこる、お金が足りない) -
内的問題:それによって生まれる感情
(例:自信を失う、人前に出るのが怖い) -
哲学的問題:その人が持つ“信念”への裏切り
(例:頑張ってるのに報われないのはおかしい)
たとえば、薄毛ケアの商品なら:
-
外的問題:「髪が薄くなってきた」
-
内的問題:「人に見られるのが恥ずかしい」「老けて見える自分がイヤ」
-
哲学的問題:「年齢を重ねても、自分らしくありたい」
これらを言葉で描いていくことで、
商品はただの“対症療法”から“人生の味方”へと格上げされる。
悪役を明確にすると、商品価値が跳ね上がる
ここで重要なのが、
「問題=敵=悪役」
として描くことである。
悪役が明確であればあるほど、
それと戦うための“武器(=商品やサービス)”が必要に見える。
逆に、
敵がボヤけていると、
武器の存在意義も薄れる。
映画で例えるなら:
-
ジョーカーがいるから、バットマンが必要
-
ヴォルデモートがいるから、ハリー・ポッターは戦う
-
ダース・ベイダーがいるから、ルーク・スカイウォーカーは成長する
広告でも、
以下のように
「敵役=問題」
を描写することが効果的だ。
広告の敵役の描き方(実例)
例1:副業サポートサービス
「せっかく副業を始めたのに、何から手を付けていいかわからない…。
情報は多いのに、結局誰も“教えてくれない”。」
→ 敵役=情報過多で迷子にさせるネット社会
例2:ダイエットサポートアプリ
「“痩せなきゃ”と頭ではわかってるのに、毎日続かない。
ダイエットは、意志が強い人しか成功しない…と思っていませんか?」
→ 敵役=三日坊主の自己嫌悪、意思力神話
例3:家計管理アプリ
「“今月いくら使ったっけ?”と思い出せないまま、
またクレジットの明細に驚く。
お金が貯まらないのは、性格のせいじゃない。」
→ 敵役=“見えない出費”と漠然とした不安
問題提起は“入口”であり、最強の接続ポイント
広告を読み始めたばかりの読者に、
いきなり商品の話をしても、共感は得られない。
まずは
「わかる、その気持ち」
と言わせることが先。
そしてその共感を生む鍵が、
“問題提起”なのだ。
問題提起 → 共感 → 解決策の提示
という流れを徹底することで、
広告は
「売り込み」ではなく
「気づきと救済」になる。
問題を描ければ、人は自分の物語として受け取る
-
問題は、広告における“敵”である
-
問題を深く掘り下げることで、共感と信頼が生まれる
-
感情(内的問題)や信念(哲学的問題)まで掘り下げると、
物語の深度が増す -
敵が明確であるほど、商品は必要とされる
ストーリーブランディングにおいて、
「あなたの敵は、私の敵でもある」
と感じさせることができれば、
それはもう、
商品という武器を手に取る理由になる。
次回は、その“武器”
――商品やサービスをどうやって
「読者の人生の中で必要なもの」
と位置付けるかを、
ガイド役(あなた)の立場から掘り下げていきます。
共感されるブランドは“助ける存在”である
──あなたの商品は読者の人生をどう変えるのか
ストーリーには必ず
「主人公」
がいる。
広告における主人公は、
あなたではない。
顧客である。
これは、
すでに前のステップでも強調してきた重要な視点だ。
では、
あなた(=ブランド、商品、サービス)は、
その物語の中でどんな役割を果たすべきなのか?
答えはひとつ。
「ガイド」だ。
あなたの商品は、
顧客が抱える問題を解決するための手段であり、
あなた自身(あるいは会社)は、
それを手渡す助け手でなければならない。
ストーリーには「ガイド」が必要だ
映画を思い出してほしい。
-
ルーク・スカイウォーカーには、オビ=ワンがいた
-
ハリー・ポッターには、ダンブルドアがいた
-
フロドには、ガンダルフがいた
どんな主人公にも、
必ず導いてくれる存在が登場する。
それが「ガイド」だ。
このガイドの役割は、こうである。
-
主人公の抱える“問題”を理解し
-
乗り越える“方法”を示し
-
必要な“道具”や“勇気”を与えること
つまり、
広告でも同じ構造が使えるということだ。
あなたは、
読者という主人公に対して、
「あなたがその敵と戦い、乗り越えるためには、これが必要です」
と語りかける存在であるべきだ。
ブランドが“ガイド”であると伝える方法
顧客に
「この人は信頼できる」
「頼ってもいい」
と思ってもらうには、
ただ商品説明をするだけでは不十分だ。
ガイドであることを証明するには、
2つの柱が必要になる。
1. 共感(私はあなたの苦しみを知っている)
まず大事なのは、共感だ。
「あなたがいま感じている不安、私も知っている」
「それに向き合って、抜け出した人たちを何人も見てきた」
「だからこそ、あなたにも伝えたいことがある」
こうしたスタンスは、売り手と買い手の壁を取り払い、
“対等な物語の登場人物”として
信頼を築くことができる。
共感を伝えるときは、
抽象的な言葉ではなく、
読者の感情や生活を具体的に描く
と効果的だ。
2. 権威(私はこの問題を解決する力がある)
共感だけでは
「良い人」
で終わってしまう。
もうひとつ必要なのが、
“この人なら任せて大丈夫”と思わせる根拠だ。
それが「権威」や「実績」である。
たとえば:
-
◯万人以上が使っている
-
テレビやメディアで紹介
-
専門家による監修
-
100件以上のレビューで高評価
-
開発までに5年かけた技術
こうした“安心材料”は、
読者が「この人(商品)についていこう」と思える土台になる。
商品を「武器」に見立てて説明せよ
ガイドであるあなたが提供するのは、
顧客(主人公)が問題と戦うための“武器”である。
この構造で説明すると、商品説明がグッとわかりやすくなる。
たとえば、こうだ:
例1:在宅副業教材
あなたは今、「副業を始めたいけど、何からやればいいのかわからない」という混乱の中にいます。
私たちが提供するのは、「何を選び、どこから手をつけるか」がすべて明確になる“地図”のような教材です。
まるで、RPGゲームで最初にもらう剣のように、この教材があなたの最初の一歩を支えます。
例2:睡眠改善アプリ
「寝ても疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚める」
そんな悩みに対して、私たちは医療と心理学に基づいた“習慣設計アプリ”を作りました。
あなたが眠りのストレスと戦うための“盾”となる存在です。
このように「戦うためのアイテム」として商品を位置付けると、
自然と“必要なもの”として受け入れられるようになる。
顧客の目に映る“あなた”はどんな人物か?
「ガイドである」とは、
単に知識やノウハウを提供することではない。
その人の人生の一部を支え、
導いてくれる存在として、
「信頼」と
「親しみ」を
同時に抱かせる存在である。
あなた自身、
何かのサービスを受けるとき、
「この人、何となく安心できるな」
「任せて大丈夫そうだな」
と感じる瞬間があるはず。
その感覚を、
広告でも表現する必要がある。
たとえば:
-
顔写真や動画を出す(親しみ)
-
ストーリーを語る(人間味)
-
丁寧な言葉で語りかける(対話性)
こうした要素が揃っている広告は、
無機質な売り文句ではなく、
“信頼できる人からの提案”
として受け入れられる。
あなたは主役ではない。導く人であれ。
-
主人公は顧客であり、あなたはガイドである
-
ガイドには「共感」と「権威」が必要
-
商品は、顧客が問題を乗り越えるための“武器”である
-
顧客の物語に「味方」として登場することで、ブランドは信頼を獲得する
あなたがどれほど素晴らしい実績を持っていても、
それを“上から目線”で語れば、読者は離れる。
逆に、“並走する存在”として語れば、自然と頼られる。
次回は、ガイドが「計画」を提示し、
読者に“道筋”を見せる方法――
証拠が弱い広告は、心に刺さらない
──信頼を確信に変える“根拠の提示法”
これまでのステップで、
あなたの広告は以下の段階を着実に進んできた。
-
無関心を乗り越え、興味を持たせ
-
疑念を払拭し、信頼を生み
-
抵抗感を乗り越えて行動意欲を高め
-
顧客を主人公とし、あなた自身はガイドの立場に立ち
-
商品は“問題を解決するための武器”として紹介された
ここまで来れば、あとは最後のひと押し──
それが、
この信頼を「確信」へと変える“証拠の提示”である。
なぜ「証拠」がなければ売れないのか?
いくら感情を動かしても、
最後に人が商品を選ぶとき、
必ずと言っていいほど
「理屈」
を求める。
これは人間の脳の構造に関係している。
人が何かを買おうとするとき、まず“感情”が動き、
次に“論理”によってそれを正当化しようとする。
たとえば、
-
「このサプリ、なんか良さそう」
→ 感情的な引き金 -
「しかも臨床データも出てるし、レビューも多いし」
→ 理性的な納得
この「納得の根拠」が弱いと、
人は無意識のうちにブレーキを踏んでしまう。
感情で買いたくなっても、
証拠がなければ安心できない。
つまり、
「証拠」
は広告の“最後の安心装置”なのだ。
証拠の提示=信頼の裏付けである
ここで言う「証拠」とは、
単にデータや数字を出すことではない。
読者が
「自分もそうなるかもしれない」
と納得できるような、
具体的で、
視覚的で、
論理的な
“裏付け”
である。
信頼を確信に変える「6つの証拠タイプ」
1. 数字と実績(社会的証明)
-
累計販売数:◯◯万本突破
-
継続率:90%以上
-
ユーザー数:月間利用者数10万人
-
満足度調査:92.4%が「また使いたい」と回答
→ 「こんなに多くの人が使っている」=安心感
2. 顧客の声・レビュー・SNS投稿(第三者の証言)
-
実名+写真つきのレビュー
-
SNSでのリアルな投稿キャプチャ
-
顧客の成功ストーリー(ビフォー・アフター)
→ 「自分と似た人が使って効果が出てる」=共感と信頼
3. ストーリーベースの事例(人間味のある証拠)
-
「42歳主婦、初めての副業で月3万円を実現した話」
-
「パパになってからの睡眠不足が、アプリで解決された実例」
→ 「それ、まるで私のこと」=感情移入からの納得
4. 専門家・有識者の推薦(権威づけ)
-
医師・弁護士・カウンセラー・研究者の監修・推薦コメント
-
資格保持者のレビュー
-
論文・臨床試験の引用
→ 「専門家が認めてるなら安心」=理性的な納得
5. メディア掲載・受賞歴(社会的認知)
-
テレビ/雑誌/Webメディア掲載実績
-
コンテスト受賞、認定マーク、業界評価など
→ 「ちゃんと評価されてるブランド」=信用の証
6. 返金保証・リスクの軽減
-
「30日間全額返金保証」
-
「初回購入者限定、1回限りOK」
-
「定期縛りなし、いつでも解約可能」
→ 「失敗しても大丈夫」=最後の抵抗感の除去
「証拠の配置」で、読者の心理状態に合わせる
証拠は、ただ並べれば良いわけではない。
配置の順番や、どのタイミングでどの証拠を出すかが重要だ。
一例:LP(ランディングページ)の構成内での証拠配置
-
冒頭:数字の実績 or メディア掲載で信頼を引く
-
問題提起後:読者に近い“お客様の声”を配置
-
商品説明後:専門家の意見やエビデンスでロジック補強
-
CTA(行動喚起)の直前:返金保証で安心を付ける
→ このように「感情→共感→論理→安心」という流れで配置すると、
読み手の不安を自然に取り除くことができる。
“証拠が弱い”広告にありがちな失敗例
【NG例1】
「良い商品です」「多くの方に喜ばれています」
→ 抽象的で、主観的で、具体性がない。
疑念が増す。
【NG例2】
「口コミ評価No.1(※当社調べ)」
→ 根拠が曖昧。比較対象が不明。
かえって信頼を損なう。
【NG例3】
「これを使えば絶対に成功します」
→ オーバーな表現は逆に胡散臭く映る。
“証拠”どころか“誇大広告”と受け取られる危険性あり。
ストーリーの中で“証拠”をどう扱うか?
証拠はただ貼り付けるものではなく、
ストーリーの中に自然に組み込むことが最も効果的だ。
たとえば、
以下のように使う。
「最初は半信半疑でした。でも、この教材を使ってみて2週間後、
Twitterで紹介した記事に“いいね”が50件ついたんです。
それがきっかけでnoteの売上が発生しました。今では、毎月3万円の副収入が生まれています。」
→ 数値、体験談、具体性、行動の変化がセットになっていて非常に強力。
証拠は「買う理由」を“腹落ち”させる最終兵器
-
感情で惹きつけた後は、理屈で納得させる
-
証拠がなければ、信頼は“共感止まり”で終わる
-
「数字」「声」「専門性」「保証」など、
証拠の種類をバランスよく用意する -
広告の文脈の中で、自然に証拠を配置することが大切
あなたの広告が、
最後の
「もう一押しが欲しい」
という読者の気持ちに応えられるかどうかは、
どれだけ証拠の設計がなされているかにかかっている。
次回は、その“納得した読者”に行動を起こさせる最終ステップ――
期限と行動を提示せよ
──今すぐ動かすために必要な「トリガー」の仕掛け方
広告とは「行動を生む装置」だ。
見てもらうだけでは意味がない。
信じてもらうだけでも足りない。
最終的には、
“動いてもらうこと”がすべて
である。
クリックされなければ、
購入されなければ、
申し込まれなければ、
どれほど完璧な構成も、
優れたコピーも、
虚しく終わる。
では、
どうすれば
「いま、この瞬間に行動してもらえる」
のか?
その答えが、このステップにある。
なぜ「今すぐ」動いてもらわなければならないのか?
人は基本的に「先延ばしの生き物」だ。
特に、
今すぐ困っていないことは、
あと回しにされる。
-
「あとでじっくり読もう」
-
「今は忙しいから週末にでも…」
-
「ちょっと考えてからにしようかな」
こう思った人の9割以上は戻ってこない。
それがWeb広告やランディングページの世界の“残酷な真実”だ。
つまり、
「今すぐ動く理由」
を与えなければ、
あなたの広告は感心されて終わりになる。
行動を生むには「緊急性」と「明快な道筋」が必要
では、
読者に今動いてもらうために、
何が必要か?
答えは2つだけ:
-
1. 緊急性の演出(今やらないと損)
-
2. 明快な行動指示(どう動けばいいかがすぐわかる)
この2つが揃っていれば、
人は
「とりあえずやってみよう」
と思うようになる。
【1】緊急性の演出:「今やらないと損する」と思わせる技術
「期間限定」
「数量限定」
「残りわずか」
――こうした表現には強力な心理効果がある。
これは「希少性の原理」と呼ばれ、
手に入りにくいものほど価値があると
脳が判断するからだ。
緊急性を演出する方法:
-
締切を明示する
-
「本日23:59まで」
-
「◯月◯日までの限定販売」
-
-
数量の限界を見せる
-
「残り7名限定」
-
「在庫あと3点」
-
-
変化を予告する
-
「来週から価格改定」
-
「次回の募集は未定です」
-
このとき重要なのは、
本当に期限や数量に限りがあること。
ウソや誇張は、
信頼を一瞬で崩壊させる。
緊急性は
「理屈」
ではなく
「感情」
で伝える
「買わなきゃ損だな」
「迷ってる時間はない」
「今しかない」
こう思わせるのは、
数字ではなく空気感だ。
表現のテンションや色、
デザイン、
フォントの大きさにも気を配ると、
より緊張感が伝わる。
【2】明快な行動指示:「どうすればいいか」がすぐわかること
読者が「いいな」と思っても、
次に“何をすればいいかわからない”と迷った瞬間に、行動は止まる。
「今すぐ申し込む」
「LINEに登録する」
「無料でダウンロードする」
「30秒で簡単エントリー」
「このボタンを押すだけでOK」
CTA(Call To Action=行動喚起)は、
“指示”ではなく
“導き”であることがポイント。
ボタンの文言ひとつで、
反応率は何倍も変わる。
よくある失敗パターン:
-
「Submit」や「送信」など、
抽象的で味気ないボタン → 行動が曖昧 -
長すぎるフォーム → 面倒になって離脱
-
ページの一番下まで読まないとCTAがない → 途中離脱が増える
解決策:
-
ボタンはできるだけ短く・具体的に・複数回配置
-
フォームは1〜2ステップに分けて簡潔に
-
目立つ色・サイズ・余白を使って目線誘導
「今やる意味」を“感情”で届ける言葉例
-
「迷っているなら、まずは試してみてください。」
-
「行動した人だけが、結果を変えられます。」
-
「1回のクリックが、あなたの未来を変えるかもしれません。」
-
「今やらなくて、いつやりますか?」
-
「このページを閉じたら、チャンスを逃すかもしれません。」
これらの一言が、
行動を躊躇している読者の背中を押してくれる。
行動の“きっかけ”は、最初の一歩をどれだけ小さくできるか
「まずは登録だけ」
「無料で試せる」
「今すぐじゃなくても、情報だけでも受け取っておく」
このように、
心理的ハードルを低く設計する
ことも重要。
例えば:
-
「メールアドレスだけでOK」
-
「LINEで友だち追加するだけ」
-
「〇〇日以内なら解約可能」
→ 「やらない理由」が見つからなくなったとき、人はようやく動く。
広告は“その場で行動”させる設計が命
-
人は放っておくと、行動を後回しにする
-
緊急性と希少性が“今動く理由”になる
-
行動指示(CTA)は、簡潔・具体的・導線的に
-
「とりあえずやってみよう」と思わせる心理設計がポイント
完璧に作られた広告でも、
最後の一押しがなければ反応はゼロ。
あなたの商品やサービスを本当に届けたい相手に、
“今”動いてもらうための設計こそ、
最重要の仕上げである。
行動を“物語の結末”にせよ
──購入はエンディングではなく、始まり
あなたの広告は、
「無関心」から「共感」へ、
「疑念」から「信頼」へ、
そして「抵抗感」から「行動」へ――
ひとつずつ感情のハードルを越えてきた。
そしてついに、
読者は“行動を起こす”というゴールにたどり着く。
…しかし、
ここで一つ、
重要なことがある。
行動=ゴールではない。
購入、申し込み、登録。
それは“終わり”ではなく、
顧客の新しい物語の
「始まり」
である。
多くの広告は、エンディングを間違えている
広告の目的は、
商品を売ること――
確かにその通りだ。
だが、
広告が「売ったら終わり」と思ってしまった瞬間に、
顧客との関係は途切れる。
本当に信頼されるブランド、
長く選ばれるサービスは、
その先のストーリーまで描いている。
つまりこういうことだ:
「あなたの人生がどう変わるのか」
「使い続けることで、どんな未来が訪れるのか」
「選んだ自分を、誇りに思えるような物語」
この“未来への期待”をしっかり提示してこそ、
広告は
「ただの販促」から
「記憶に残る体験」へと昇華する。
購入は「新しい物語の幕開け」である
物語の終わりで、
主人公は成長する。
敵を倒し、
自分を乗り越え、
新しい日常を手に入れる。
同じように、
広告のエンディングでも、
「読者が何を得て、新しい自分になるのか」
を描かなければならない。
たとえば:
-
副業教材 → 「副収入を得て、会社に依存しない自分へ」
-
健康サプリ → 「毎朝スッキリ起きて、仕事も家庭も全力で楽しめる生活へ」
-
ダイエットアプリ → 「自信を取り戻し、鏡の前の笑顔が増える日々へ」
ここで意識したいのは、
“商品を使って得られる”ベネフィットのその先。
つまり「人生レベルでの変化」だ。
「購入=選択の証」として、誇らしいものにする
買い物をするということは、
“何かを選び、何かを選ばなかった”ということ。
その選択が、読者にとって
「自分は良い決断をした」
と思えるようにするには、
購入後の世界を魅力的に提示しなければならない。
たとえば:
-
「この教材を選んだあなたは、もう“迷わない自分”です。」
-
「毎日スッキリ目覚められるようになったら、人生が変わります。」
-
「この一歩が、5年後のあなたをつくります。」
→ 商品ではなく、“選んだあなた”を讃える言葉が刺さる。
これは購買体験を
「誇らしい記憶」
にする演出であり、
次の購入や、
リピート、
紹介につながる“感情の残像”を生む。
最後の“一文”に宿る、ブランドの物語
広告の最後の一文は、
映画で言えば「ラストシーン」、
小説で言えば「エピローグ」にあたる。
ここが弱いと、
全体がぼやけて終わってしまう。
ここが強ければ、
読者はページを閉じたあとも、
「なんか、いいな」
と感じた記憶だけが残り続ける。
例:
-
「今日、あなたの物語が少しだけ前に進みますように。」
-
「迷った今日が、未来の自分に感謝される日になりますように。」
-
「これは、あなたの人生に“選んでよかった”を増やす選択です。」
→ “一文でエンディングを締める力”こそ、広告を作品に変える技術である。
顧客の物語に“継続して関わる”視点を持て
広告は単発で終わるものではない。
本当に強いブランドは、顧客の人生に寄り添い続ける。
-
購入後のメール
-
同封する手紙
-
初回開封時の案内
-
継続フォローのLINEメッセージ
こうしたタッチポイントのすべてが、
顧客の物語の“次の章”をつくっていく。
つまり、広告は第一章のプロローグにすぎない。
あなたが提供すべきなのは、
“最初のページ”ではなく
“シリーズとして続く物語”だ。
広告は「売って終わり」ではなく、「始まりを作る装置」である
-
購入=読者の人生の転換点である
-
「選んでよかった」と思わせるエンディング設計が重要
-
商品ではなく“その後の世界”を語ることで、記憶に残る
-
最後の一文でブランドの哲学を届ける
-
継続した関係構築が、広告の真の成功を決める
すべての広告は、
誰かの人生の中で小さな“ターニングポイント”になる可能性を秘めている。
そしてその一歩を踏み出してくれた人に対して、
「ここからが始まりです」というストーリーを、
ぜひあなたの言葉で描いてほしい。
【具体的な応用例】
以下に、
実際にこのテンプレートをどのように応用できるか、
業種別に一部をご紹介します。
■ 美容・健康系(スキンケア、サプリ、整体、ジムなど)
主人公のペルソナ選定方法
対象は
「加齢や体調、外見の変化に不安やストレスを抱えている人」。
年齢は30代後半から50代女性が中心。
子育てや仕事が落ち着き、
自分の時間が持てるようになった反面、
体力の衰えや肌の老化などが目立ってきた層。
「昔の自分と今の自分にギャップを感じている」
人を選ぶと、
感情移入しやすい。
具体的な例:
・40代女性。子どもが中学生になり、鏡の中の自分が「老けた」と感じる
・生理やホルモンバランスの乱れに悩み、寝起きもだるい
・仕事では若い部下が増え、見た目へのコンプレックスが強まっている
悪役の問題
「年齢を重ねるごとに、体も肌も“なんとなく衰えていく”こと」。
これは目に見えない“緩やかな不調”で、
放っておいても命に関わらないが、
気持ちを沈ませ、
自己肯定感を奪う強い悪役となる。
この問題の怖さは、
「日常に馴染みすぎていて気づきにくい」こと。
疲れが取れない。
肌にツヤがない。
イライラする。
何かに対して前向きになれない。
これらは全部つながっており、
根本原因が見えないまま、
何年も放置されがち。
その問題の気づかせ方
読者に
「自分のことだ」
と思わせるには、
日常のシーンで描写するのが効果的。
例えば:
-
朝、鏡を見たときに「こんなに目元、たるんでた?」とハッとした
-
夜、子どもが寝静まった後、スマホを見ていると肌のくすみが目立って落ち込む
-
洋服を選ぶときに「昔はもっと明るい色が似合ったのに…」と感じる
このように、
共感されやすい具体的な描写で
「気づきのきっかけ」
を演出する。
問題の原因
ほとんどの場合、
生活習慣やストレス、
ホルモンバランスの乱れなどが複合的に絡んでいる。
ただし、
広告の中でその原因を“学術的に説明する”必要はない。
むしろ
「自分が悪いわけじゃなかったんだ」
と思わせることが大切。
例えば:
-
「年齢による変化は避けられない。
でも、ちゃんとケアすれば防げるんです」 -
「あなたが怠けているのではなく、
体の内側が“助けを求めていた”だけなんです」
こう伝えることで、
読者は“自分を責める感情”から解放される。
商品の役割
ここで商品は、
問題を解決するための“武器”として登場する。
スキンケアなら
「肌にうるおいを与える」
という機能だけでなく、
「自分にもう一度自信を持てるようになる」
という“心の回復”を果たす存在として描く。
商品はあくまで“目的”ではなく、
“手段”である。
目的は
「私、まだキレイになれる」
という確信を取り戻すこと。
使うことで想像できる未来
・朝、鏡を見るたびに笑顔になれる
・同世代の友人に「なんかキレイになった?」と言われる
・メイクや洋服選びが楽しくなる
・外に出るのが億劫じゃなくなる
・写真に映る自分が好きになる
このように
「日常の質が上がる未来」
を具体的に描写することで、
商品の必要性が高まる。
得られるベネフィット
・自分に自信が持てるようになる
・他人の目を気にせず、自然体でいられる
・“年齢に抗う”のではなく、“年齢を受け入れて輝く”という感覚
・行動や感情がポジティブに変わる
このように、
感情的・内面的な変化をしっかり描くのがポイント。
美容商品や健康食品は、
「効果が出た」という声より、
「人生が明るくなった」という声の方が、
共感を呼ぶ。
使ったことでどのように変われるか
・外見だけでなく、内面も変わったと実感できる
・「どうせ私は…」という諦めが、「私もまだできる」に変わる
・毎日の小さな行動(出かける・話す・笑う)が自然に前向きになる
・その変化が、家族や職場、友人との関係にも良い影響をもたらす
変化は、
外見から自信へ、
自信から行動へ、
行動から人生全体へと広がっていく。
応用のアドバイス
美容・健康系の広告では、
「効果」や「成分」だけを訴えると埋もれやすい。
だからこそ、
「人間ドラマ」や「人生の転機」
として描くことが重要。
同じ化粧水でも、
「40代の私が、自信を取り戻すまでのストーリー」
にするだけで共感と購入率が高まる。
また、
画像やビフォーアフターに頼らず、
「言葉だけで変化を描く」
ことも大きな武器になる。
なぜなら、
読者の多くは、
ビジュアルよりも「気持ち」に動かされて行動するからである。
教育・講座系(オンライン講座、資格取得、個別学習サポートなど)
主人公のペルソナ選定方法
ターゲットは
「今の自分を変えたいと思っているが、何から始めていいかわからない人」。
具体的には以下のような人物像が有効です。
・30代〜40代の社会人。仕事に不安があるが、スキルも経験も自信がない
・育児が一段落し、再び社会に出たいと考えている主婦
・「このままでいいのか」と漠然と感じながら日々働いている若手ビジネスマン
つまり、
「人生を変えたいという思いはあるが、手段が見つからない人」
を主人公にすることが重要です。
悪役の問題
この業界の悪役は、
「変わらなきゃいけないと分かっているのに、動けない自分」です。
これは、
「時間がない」
「やっても無駄」
「もう遅いかもしれない」
といった無数の自己否定の言葉として表面化します。
さらに、
「勉強する習慣がない」
「昔の挫折経験」
が心の奥底にブレーキとして残っていることもあります。
この内なる悪役をきちんと見せることが、
物語としての説得力を生みます。
その問題の気づかせ方
ここでは、
「共感」で読者を引き込む必要があります。
たとえば、
以下のような描写が効果的です。
・同僚がスキルアップのために勉強を始めているのを見て焦りを感じた
・子どもが宿題をしている横で、自分は何もしていないと気づいた
・求人情報を見たとき、どの条件にも当てはまらない自分にがく然とした
こうしたシーンは
「あるある感」を生み出し、
「自分にも心当たりがある」と感じさせることができます。
問題の原因
「行動できない自分」を責めている人は多いですが、
原因の多くは
「方法を知らない」
「選択肢が見えていない」
ことにあります。
ここでは、
「あなたが悪いのではなく、道が見えていなかっただけなんです」
と伝えることで、
読者はふっと肩の力を抜きます。
さらに、
「学ぶ=苦しいもの」
という思い込みを取り除く構成も重要です。
「勉強=暗記・受験」
という先入観に縛られている層には、
「学びは人生を再設計するツールです」
という新しい定義を提示します。
商品の役割
商品は、
“道を示してくれる地図”であり、
“先導してくれるガイド”でもあります。
その商品を使うことで
「今の自分でもスタートできる」
「一人じゃない」
と感じられるように演出します。
講座の中身や内容を並べるよりも、
「受講者がどのような心理で申し込んだか」
「何が後押しになったのか」
をストーリーで見せるほうが刺さります。
使うことで想像できる未来
・新しいスキルを身につけ、転職や副業に挑戦できるようになる
・学んだことを活かして、家計の支えになるような仕事を選べる
・“学びを続ける自分”に対して誇りが持てるようになる
・SNSやコミュニティで「この人はちゃんと勉強してる」と認識される
このような未来は、
読者にとって“ワクワク”よりも“安心”が伴っている方が強く刺さります。
得られるベネフィット
・将来に対する不安が減る
・自分にできることが増える
・「今の自分が一番成長している」と感じられる
・誰かに依存しない働き方を目指せる
・「学ぶ=楽しい」と思えるようになる
ここでは
「資格を取る」ことそのものより、
「その行動がもたらす自信」や
「自己像の変化」を
丁寧に描写するのがポイントです。
使ったことでどのように変われるか
・自信がなかった人が「人前で自分のスキルを話せるようになった」
・「新しい仕事に挑戦する勇気が持てた」
・「子どもに“勉強って面白い”と堂々と言えるようになった」
・「時間の使い方が上手くなり、学びが日常の一部になった」
こうした変化を、
1人の受講者の視点でストーリー仕立てにすることで、
説得力と共感が高まります。
応用のアドバイス
この業界では
「内容が多すぎると逆に不安を煽る」
傾向があります。
「カリキュラムはこんなにあります」
「学習時間は○○時間です」
と詰め込み型の広告では、
読む側が疲れてしまうこともあります。
むしろ、
「学びが自然に身につく流れ」
「続けられる設計」
「挫折させない工夫」
など、
“心の設計”に重きを置いた伝え方が有効です。
また、
「学ぶ理由」ではなく、
「学んだ後の生き方」を見せる方が、
購入や申し込みに直結しやすくなります。
恋愛・占い・自己啓発系(恋愛講座、スピリチュアル鑑定、メンタルサポート、カウンセリング等)
主人公のペルソナ選定方法
対象は、
「自分自身の在り方に悩み、今の状況を何とかしたいと感じているが、解決策が見つからない人」。
具体的には以下のような人物像が当てはまります。
・30代独身女性。恋愛に自信が持てず、「またうまくいかないかもしれない」と不安に思っている
・40代のバツイチ男性。再婚したいが、過去の失敗や自信のなさから踏み出せない
・20代後半の女性。SNSでキラキラした人たちを見て、どんどん自分が小さく思える
共通しているのは、
「人に言えない悩み」
「心の奥にある孤独感」
「自分自身を変えたいという思い」
です。
悪役の問題
このジャンルにおける悪役は、
「繰り返される自己否定」
「運命に翻弄される無力感」
「誰にも分かってもらえない孤独」
です。
それは日常の中に自然に溶け込んでいて、
見えにくい分、
根深く、
長く引きずられてしまう傾向があります。
また、
「一歩踏み出したいのに、怖くて動けない自分」や、
「過去の出来事から逃れられない自分」が敵となることも多く、
読者自身が悪役になってしまうことすらあります。
その問題の気づかせ方
ここでは、
「あなたの抱えているその感情は、異常ではない」
と伝えることが非常に重要です。
たとえば、
以下のような描写が効果的です。
・LINEの未読が続いている相手に気を遣いすぎて、気疲れしてしまう自分がいる
・幸せそうなカップルを見ると、自分がダメな人間に思えて涙が出そうになる
・誰かに「大丈夫?」と言われるたびに、本当は大丈夫じゃないのに「うん」としか言えない
このような“言葉にならないモヤモヤ”を先に言語化することで、
読者は
「あ、私のことを分かってくれてる」
と心を開きます。
問題の原因
多くの場合、
問題の本質は
「過去の失敗体験」や
「他人との比較」
「愛されることへの不信」など、
外側の要因ではなく内面的な要素にあります。
そのため、
解決策は単なる“正解”ではなく、
“気づき”や“許し”といった心の変化に置かれます。
ここでは、
「あなたが悪いのではなく、そういう背景があっただけ」
と優しく受け止めるスタンスが求められます。
商品の役割
商品やサービスは、
「新しい視点を与えるレンズ」であり、
「過去と向き合い、前を向くきっかけ」です。
占いや恋愛講座、
自己啓発セッションは、
読者が“これまでの自分”と“これからの自分”をつなぐ
「小さな扉」
として描くと効果的です。
“運命を変える”のではなく、
“自分の選択に自信を持てるようになる”という流れにすると、
より現実的かつ共感を呼びます。
使うことで想像できる未来
・恋愛に対する思い込みが外れ、自然体で人と向き合えるようになる
・「誰かに選ばれる自分」から、「自分で自分を選ぶ自分」になれる
・不安を感じるたびに見返す“お守りのような言葉”を手に入れる
・心のざわつきが消え、日常に穏やかさが戻る
未来の変化は“環境”ではなく“心”にフォーカスします。
派手な演出は不要で、
「呼吸が深くなった」
「寝る前にホッとできた」
というような変化が信頼を生みます。
得られるベネフィット
・自分の気持ちに正直になれるようになる
・「愛されないかもしれない」という恐怖から解放される
・毎日が“誰かの目線”ではなく、“自分の気持ち”で決められるようになる
・言葉にできなかった想いが整理されて、「今の自分でいい」と思えるようになる
ベネフィットは
「変われること」ではなく、
「今の自分を受け入れられるようになること」。
その変化は静かだけど、
確かなものとして丁寧に描写する必要があります。
使ったことでどのように変われるか
・自己否定ばかりだった自分が、自分の気持ちを尊重するようになった
・恋愛がうまくいかなくても、「私は価値のある人間だ」と思えるようになった
・夜眠れなかった日々が、感情ノートと一緒に過ごすことで少しずつ穏やかになった
・「答え」を求めるのではなく、「今の自分のままで進んでみよう」と思えるようになった
これらの変化を、
実在するような人物に語らせるストーリーとして構成することで、
「私にもできるかも」
と思わせることができます。
応用のアドバイス
この分野では、
「過剰な成功例」や
「派手な演出」は
逆効果になります。
人が求めているのは“奇跡”ではなく、
“心の安定”です。
そのため、
広告文では
「問題→商品紹介→購入へ」
の流れではなく、
「共感→気づき→希望→商品」
の流れが自然で効果的です。
また、
言葉づかいは
「寄り添う」
ことが大前提。
読者は傷つきやすい状態で読みに来ています。
ですので、
「変われます」
「あなたもできます」
ではなく、
「ゆっくりでいい」
「もし、あなたが望むなら」
という柔らかいトーンが必要です。
不動産・暮らし・家系(空き家管理、賃貸管理、リフォーム、片付け、ライフサポートなど)
主人公のペルソナ選定方法
ターゲットは、
「持ち家や家族の家に関わることで“責任”を感じているが、
何から手を付けていいか分からない人」。
感情の起点は、
「面倒」
「不安」
「罪悪感」
といった“心のひっかかり”です。
具体的なペルソナ例:
・50代の会社員。親が亡くなり、実家が空き家になっているが手続きも片付けも止まったまま
・40代の女性。高齢の親が住む家のリフォームや掃除を自分一人で抱えている
・30代のシングルマザー。賃貸住宅の原状回復費用や設備の修繕で悩んでいる
共通しているのは、「住まい=暮らし=家族」という感情的な要素と、「放っておくと面倒になる」という不安です。
悪役の問題
この業界における悪役は、「手が付けられないまま時間が過ぎること」、
そして「面倒な作業を一人で抱えることによる精神的・物理的負担」です。
たとえば:
・空き家がどんどん劣化しているが、放置してしまっている
・片付けたいけど、思い出が詰まっていて捨てられない
・業者に頼むのも気が引けて、結局何もしないまま
・家族と意見が合わず、話すのも避けている
このような“目を背けたくなる現実”が、
感情の中で静かに悪化していく構造を描きます。
その問題の気づかせ方
気づきを与えるには、
「何もしていないとどうなるか」
を具体的に、
しかし煽らずに見せることが大切です。
たとえば:
・空き家の窓ガラスが割られ、不法侵入の危険性が出てきた
・親が転倒したのは、滑りやすい浴室の段差が原因だった
・相続の話を避けていた結果、兄弟間でトラブルに発展した
これらの描写を通じて、
「これは放っておいてはいけない問題なのだ」
と静かに認識させていきます。
問題の原因
原因は、
「面倒で複雑に見える」
「何から始めたらいいか分からない」
「感情が絡むことで手をつけにくい」
という構造的な問題です。
「問題が大きくなってからでは遅い」
と感じていても、
誰にも相談できない、
業者に頼むのが恥ずかしい、
自分の責任のように思えてしまう、
という心理的ブロックが存在しています。
ここでは
「放置してしまうのは当然」
「誰でも同じことで悩む」
というスタンスで共感から始めることが重要です。
商品の役割
商品やサービスは、
「感情的に煮詰まった状況に“中立かつ安心な第三者”として介入する役割」を担います。
「状況を整理してくれるプロ」や、
「家族でもないから話しやすい存在」として描くと、
サービスを依頼するハードルが大きく下がります。
たとえば:
・空き家管理なら「あなたに代わって定期的に巡回し、問題を報告する伴走者」
・リフォームなら「老後の安全と安心をデザインするアドバイザー」
・片付け代行なら「思い出と向き合いながら、未来を見据えて一緒に整理してくれるパートナー」
「作業をする人」ではなく、
「人生の整理を助ける人」として描くことが差別化になります。
使うことで想像できる未来
・空き家のことを考えるたびに重くなっていた気持ちが、安心感へと変わる
・「いつかやらなきゃ」と思っていた後ろめたさが消え、前向きな気持ちになれる
・高齢の両親が「ありがとう」と笑ってくれるようになった
・自分の判断に自信が持てるようになり、家族と前向きに話し合えるようになる
このような変化は、
実際にサービスを使った「その後」の日常を描くことで、
説得力が出てきます。
得られるベネフィット
・家族に頼られすぎず、プロに相談することで精神的に解放される
・物理的な負担だけでなく、感情的な“引っかかり”が取れる
・面倒ごとに蓋をしなくても済む安心感
・「自分の暮らしを整える力がついた」という自己肯定感
このベネフィットは、
“作業の代行”ではなく、
“精神的な支援”として描くことで深みが増します。
使ったことでどのように変われるか
・ずっと「誰かに迷惑をかけるかも」と思っていたが、今は「自分で選べる」と思えるようになった
・一人で悩んでいたことが、プロの言葉で一気に整理された
・自分では処理できなかった親の荷物を、一緒に仕分けしたことで気持ちの整理がついた
・「やらなきゃいけないこと」が「やってよかったこと」に変わった
変化の本質は、
「背負っていた感情の重さが軽くなったこと」。
これは非常に大きな価値であり、
言葉にして丁寧に伝えるべきです。
応用のアドバイス
不動産や暮らし系の広告は、
「安心」
「信頼」
「人柄」
が何より大切です。
ですので、
「どんな作業をしてくれるか」
ではなく、
「誰が、どんな想いで、どんな対応をしてくれるか」
にフォーカスしたストーリー構成が有効です。
また、
「家」
「暮らし」
「家族」
は感情と深く結びついているため、
論理で押すより、感情の整理を助ける“共感軸”の広告が心を動かします。
士業・代行・BtoB系(行政書士、税理士、代行業、業務コンサル、業務委託など)
主人公のペルソナ選定方法
この分野では、
ペルソナは
「業務の負担を減らしたい経営者・個人事業主」
「専門知識がない中で困っている人」
「誰かに頼りたいが、信頼できる相手が見つからない人」
が中心になります。
具体例としては以下の通りです:
・創業して間もない個人事業主。補助金や許認可について調べてみたが、情報が多すぎて混乱している
・中小企業の経営者。記帳、労務、契約書作成などの“面倒だけど重要”な業務を抱え続けている
・副業で物販を始めた会社員。開業届、青色申告、納税手続きなどが初めてで不安
共通点は、
「業務に時間を取られて本業に集中できていない」
ことと、
「自分でやるには荷が重い」
と感じている点です。
悪役の問題
この分野での悪役は、
「煩雑な事務作業」
「法律・制度・書類といった“よく分からないもの”」
「自分で抱え込んで疲弊する日常」
です。
さらに、
「相談できる相手がいない」
「過去に業者とトラブルがあった」
という不信感も根深く、
見えない敵として存在します。
たとえば:
・役所に相談したが、聞き慣れない言葉ばかりで結局何も進まなかった
・見積り依頼をしただけで、後から営業の連絡がしつこく来た
・「契約書の雛形はネットにあるから大丈夫」と思っていたらトラブルになった
こうした“過去の小さな痛み”を掘り起こして、
読者に
「だから今も動けていないんだ」
と気づかせるのが効果的です。
その問題の気づかせ方
次のような描写で、
現状の
「負担」
「不安」
「不信」
を言語化すると共感を得られます。
・本業の合間に調べ物ばかりして、1日が終わってしまった
・気づけば、毎月のルーティン作業に追われて“攻め”の時間が取れない
・誰かに頼みたいけれど、「余計に面倒になったらどうしよう」と思ってしまう
このように、
読み手が
「自分のことだ」
と感じる場面をリアルに切り取ることで、
心の扉を開きやすくなります。
問題の原因
大きな原因は、
「自分で何とかしなければ」
という思い込みと、
「業者への不信感」
です。
特に、
士業やBtoB業務は“正解が見えにくい”領域であるため、
「何を依頼すればいいか分からない」
「相談するだけでお金がかかりそう」
といった不安が付きまといます。
ここで重要なのは、
「あなたが悪いのではなく、分かりにくくなっている仕組みの方に問題がある」
と伝えることです。
商品の役割
商品やサービスは、
「情報や作業の迷路を抜けるための“伴走者”」
です。
つまり、
全部やってくれるのではなく、
必要な道を一緒に選び、
進めてくれる”存在として描くことが有効です。
たとえば:
・行政書士なら、「法律と現実の間に立ち、最短ルートを示してくれる道先案内人」
・記帳代行サービスなら、「税務の不安をゼロにし、本業に集中できる環境を整える人」
・業務委託なら、「専門性とスピードを持って、責任を背負ってくれる右腕」
このように、
商品は解決手段ではなく、
安心を得るパートナーであることを強調します。
使うことで想像できる未来
・「何をすればいいのか」が明確になり、迷いが消える
・今まで手をつけられなかった業務が、自然と整理されていく
・「この人に頼めば大丈夫」という存在ができ、精神的に余裕が持てる
・業務負担が減り、空いた時間で売上アップや新しいチャレンジができる
未来の描写は、
「心の安心」
「頭の整理」
「行動の加速」
の3点セットで構成すると説得力が増します。
得られるベネフィット
・“専門外のこと”にエネルギーを奪われずに済む
・「いつかやらなきゃ」のストレスから解放される
・書類や制度に悩まされる日々が終わる
・自分ひとりで抱え込まずに済む「信頼できるパートナー」ができる
特にこのジャンルは、
「結果」よりも
「安心感」や「信頼」
が最も大きなベネフィットになります。
使ったことでどのように変われるか
・申請や手続きに追われることがなくなり、売上向上に集中できるようになった
・「やらなきゃ…でも分からない…」という状態から抜け出せたことで、精神的に楽になった
・“何かあったときに頼れる存在”ができたことで、ひとりの不安が消えた
・本業の成長が加速し、自信を持って経営に向き合えるようになった
変化は
「知識が増える」や
「スキルが伸びる」ではなく、
「自分の人生や仕事に安心と余裕が戻ること」
として描きます。
応用のアドバイス
士業や代行系の広告でやってしまいがちなのが、
「専門用語を並べて信頼性を出そうとすること」
です。
しかし、
読者は知識よりも安心できる人かどうかを見ています。
ですので、
次の3点を意識すると反応率が上がります。
-
言葉は専門的にせず、“日常語で説明”する
-
商品説明の前に、“なぜこの仕事をしているのか”を語る
-
解決策よりも、“相手の状況や気持ちを理解している”ことを伝える
また、
「行動することで得られる自由」や
「手放せる不安」
にフォーカスすることで、
読者はただの依頼ではなく前向きな選択としてサービスを捉えます。
ファッション・ジュエリー・装飾品(服、アクセサリー、靴、バッグ、時計、帽子など)
主人公のペルソナ選定方法
ターゲットは、
「今の自分を変えたい」
「印象を良くしたい」
「気分を上げたい」
と考えているが、
日常の中で自己表現の方法が分からない人。
特に感情的なきっかけに左右される傾向が強く、
選ばれる理由は
「機能性」よりも
「意味性」「演出性」が中心となります。
具体的なペルソナ例:
・30代後半の女性。出産や育児を経て、「自分らしさ」が分からなくなっている
・20代の男性。社会人になり、好印象を与える身だしなみに気を遣うようになった
・40代女性。久々に会う旧友との食事会に、年齢相応の“品のあるアクセサリー”を探している
共通しているのは、「今の自分に、何か物足りなさを感じていること」です。
悪役の問題
この分野における悪役は、
「自信のなさ」
「印象の不安定さ」
「見た目に対する他人の評価への依存」
です。
また、
「今さらおしゃれしても意味ないかも」
「年齢的にもう…」
といった自己否定も、
強力なブレーキとして存在します。
具体的には以下のような思考が敵になります。
・「似合っていないと思われたら恥ずかしい」
・「おしゃれしても誰も気づいてくれない」
・「あの頃はよかったけど、今の私は…」
こうした過去の自分との落差を無意識に比較して苦しんでいる人が多いことが特徴です。
その問題の気づかせ方
ファッション系の広告では、
読者の感情に寄り添うような表現が効果的です。
たとえば:
・クローゼットに服はたくさんあるのに、
「着たいもの」がひとつも見つからなかった朝
・ふとした瞬間に、街を歩く同世代の女性がまぶしく見えた
・会話中に「それ似合ってるね」と言われたとき、
自分が驚いてしまった
こうした描写は、
「感情を揺さぶるリアルな瞬間」として、
読者の共感と自己投影を引き出します。
問題の原因
根本的な原因は、
「自分に似合うものが分からない」
「何を選んでいいか分からない」
「そもそも、自分が選んでいいのか不安」
という感情です。
また、
かつての似合っていたスタイルを脱ぎ捨てられず、
新しい自分を探せずにいる、
という心理もあります。
広告では、
「似合う服がないのではなく、似合っていいと思える自分を認められていないだけ」と、
視点を変える言葉を投げかけることで読者の心を動かせます。
商品の役割
商品は、
単に「身につける物」ではなく、
「新しい自分と出会うきっかけ」として登場します。
ファッションやジュエリーは、
「外見を整える道具」ではなく、
「内面を解放するトリガー」です。
たとえば:
・アクセサリーなら「過去の自分に敬意を払いながら、これからの自分に光を当てる存在」
・服なら「まだ眠っている魅力を引き出してくれるスイッチ」
・バッグや靴なら「一歩先に進む勇気をくれるアイテム」
このように、変化を起こすスイッチとして商品を位置づけると、意味が生まれます。
使うことで想像できる未来
・友人に「そのコーデ、似合ってるね」と自然に褒められた
・買い物に出かけるとき、気分が少しだけ上向きになる
・写真に映る自分が「他人」ではなく「自分らしく」見える
・着ている服や身につけたジュエリーが、気分を整える“お守り”になる
このように、
商品を使ったことで
「自分が変わる」
「周囲の反応が変わる」
ことを、
具体的な情景として描きます。
得られるベネフィット
・自分の印象に自信が持てるようになる
・「この服(アクセサリー)は、自分を表現してくれる」と思えるようになる
・“似合っているか”より“自分が好きかどうか”で選べるようになる
・「年齢を重ねること=魅力が増すこと」という前向きな感覚が手に入る
ここでは、
「若返る」
「キレイになる」
といった表面的な言葉よりも、
「自分を大切にする感覚が芽生える」
といった心の変化を強調するのが鍵です。
使ったことでどのように変われるか
・外見に気を遣うことが“誰かのため”ではなく、“自分のため”になった
・身だしなみが整うことで、仕事にも前向きな姿勢で取り組めるようになった
・これまで挑戦できなかった色やデザインに自然と手が伸びるようになった
・見た目を変えただけで、人間関係にも小さな変化が生まれた
変化の本質は、「自分を肯定できるようになること」。
商品が変えるのは“外側”ではなく、“見え方と感情”です。
応用のアドバイス
ファッションやジュエリーの広告では、
「価格」
「素材」
「デザイン」
などの情報に終始する広告が多く見られます。
しかし、
それだけでは共感も記憶にも残りません。
大切なのは、
「そのアイテムが、どんな物語をまとうか」。
・なぜこれを選んだのか
・どんな日常の中で使いたいと思ったのか
・どんな気持ちの変化を起こしたのか
これらをストーリーとして伝えることで、
読者は
「この商品は、私の物語にも似合うかもしれない」
と思うようになります。
IT・Web・ツール系(業務効率化ツール、アプリ、SaaS、Webサービス、クラウドサービスなど)
主人公のペルソナ選定方法
この分野のターゲットは、
「手作業や非効率な業務に時間を奪われている人」
「複数の業務を抱え、優先順位のつけ方に迷っている人」。
ITリテラシーの高低に関係なく、
「もっと楽になりたい」
「自動化したい」
「管理しやすくしたい」
と考える層が対象になります。
具体的なペルソナ例:
・社員5〜30名規模の中小企業の経営者。現場と管理の間に入って業務が逼迫している
・フリーランス。案件管理や請求業務に時間を取られ、本業に集中できていない
・個人店舗のオーナー。顧客管理や在庫管理を紙やエクセルで行っているが、限界を感じている
共通点は、
「業務をラクにしたいけど、何を使えばいいか分からない」
「道具は欲しいが導入の手間が不安」
と感じていることです。
悪役の問題
この分野における悪役は、
「非効率な手作業」
「属人化した業務」
「アナログ管理によるミスや抜け漏れ」
「複数ツールの分散」
です。
また、
「今のままでも回っているから変えられない」
「導入が面倒そう」
「自分に扱えるか分からない」
といった“未来の不安”も障壁になります。
これらの悪役は、
「気づいてはいるけど、見て見ぬふりしている現実」
です。
だからこそ、
「あなたが悪いのではない。仕組みが不便なだけなんです」
と問題の所在を外に置くことが効果的です。
その問題の気づかせ方
以下のような描写を入れると、読者が「まさにそれ」と気づきやすくなります。
・月末になると、請求漏れや入金管理で毎回バタバタしている
・チームメンバーが休むたびに、「どこまでやってたの?」から始まる
・「とりあえずエクセル」で乗り切ってきたが、取引先が増えて収拾がつかなくなってきた
“面倒くささ”や“繰り返しのストレス”にスポットを当てることで、
問題が現実的に浮き彫りになります。
問題の原因
最大の原因は、
「効率化=複雑で難しそう」
という思い込みです。
本当は
「便利にする道具」なのに、
「手間が増える」と誤解されている。
もうひとつは、「今すぐ困っていないから後回し」になる特性。
広告では、
「難しそうに見えることを、シンプルに変えられる」
ことと、
「先延ばしが未来の損失を生む」
ことの両方をやさしく伝える必要があります。
商品の役割
商品は、
「業務の“めんどくさい”を1クリックで消してくれる相棒」
です。
便利なツールであるだけでなく、
「判断・行動・記憶といった“脳の疲労”を軽減するサポート役」
として位置づけるのがポイントです。
たとえば:
・SaaSツールなら「社内の情報を“迷子”にしない地図のような存在」
・クラウドアプリなら「複数人でもストレスなく進められる“業務の交通整理係”」
・AIチャットボットなら「問い合わせ対応の“疲弊”を代わってくれる秘書」
商品は
「管理」
ではなく
「解放」
をくれるものだと認識させる必要があります。
使うことで想像できる未来
・毎月バタバタしていた作業が、数クリックで終わるようになった
・業務の流れが“見える化”され、誰が何をやっているか一目で分かるようになった
・従業員やチームメンバーが、自律的に仕事を進められるようになった
・「このツールがあってよかった」と、社内の空気が変わった
未来は
「数字」
ではなく
「日常の感情」
で描くと、より伝わりやすくなります。
得られるベネフィット
・本業に集中できる環境が整う
・“ヒューマンエラー”を減らせる安心感が手に入る
・新しく人を雇わなくても、作業量が1/2になる
・「やることが分からない」をなくし、進捗に対するストレスが消える
特にIT系ツールでは、
「できること」より
「やらずに済むこと」に
フォーカスした表現が強く響きます。
使ったことでどのように変われるか
・日々のあれ、やったっけ?が消えたことで、精神的な余裕が戻った
・クライアントへの対応が早くなり、信頼と受注が増えた
・自分がいなくても会社が回る状態がつくれた
・気づいたら「ツールに任せていいこと」と「自分がやるべきこと」の線引きができるようになった
このように、
「成長」
ではなく
「安定」「回復」「整備」
がキーワードになります。
応用のアドバイス
IT・Web・ツール系は、
機能説明に陥ると読まれません。
重要なのは、
「誰の、どんな面倒を、どう減らすのか」。
そして
「導入によって何が楽になるのか」
を感情の言葉で伝えることです。
・難しくなさそう
・やってくれそう
・自分にもできそう
この3つを、
広告の中で自然に感じさせられれば、
反応は一気に高まります。
また、
無料体験やデモがある場合は、
「試すハードルが限りなく低い」
ことを明示しましょう。
読者の多くは、
「いいな」
と思っても
「操作に不安がある」
ことで足を止めているからです。
このように、
IT・Web・ツール系の広告は
「便利さ」を超えて、
「感情の摩耗を防ぐツール」としての物語にすることで、
多くの共感と導入意欲を引き出せます。
趣味・体験・レジャー系(習い事、ワークショップ、旅行、アウトドア体験、非日常サービスなど)
主人公のペルソナ選定方法
この分野では、
ターゲットは
「日常に退屈さやストレスを感じている人」
「刺激や癒しを求めている人」
「やってみたいけど行動できていない人」
です。
どの世代でも共通して、
「非日常」「自己解放」「小さな冒険」
への欲求がベースにあります。
具体的なペルソナ例:
・40代の会社員男性。休日は家でYouTubeを見るだけ。最近「このままでいいのか」と感じ始めた
・30代の主婦。子育てに追われ、自分の楽しみを後回しにしてきたが、少しだけ自分の時間が欲しくなってきた
・大学生。日々の講義とバイトに追われていて、心がワクワクすることが足りないと感じている
共通するのは、
「刺激が欲しい、でも不安」
「何かを始めたいけど、理由がないと動けない」
という心理です。
悪役の問題
このジャンルにおける悪役は、
「平凡な毎日」
「時間に追われる日常」
「心のマンネリ化」
です。
また、
「どうせ自分にはできない」
「もう遅い」
「一人だと不安」
といった行動へのブレーキも隠れた敵となります。
たとえば:
・カレンダーに、楽しい予定がひとつもない
・SNSで楽しそうな投稿を見ては、自分をつまらない人間だと思ってしまう
・「何かを始めること」が、むしろ気が重く感じる
これらは
「自分でも気づいていなかった疲れ」
のようなもの。
読者が自分で認識していない感情に言葉を与えることが第一歩です。
その問題の気づかせ方
以下のような描写が効果的です。
・スマホを開いては閉じ、特に何もすることなく休日が終わってしまった
・子どもやパートナーは楽しそうなのに、自分だけ“置いていかれている感覚”がある
・「変わりたい」と思っても、「何をすればいいか」が思いつかない
このように、
言語化できない不満を代弁することで、
「もしかして自分のことかも」
と気づいてもらえます。
問題の原因
問題の本質は、
「自分のための行動に理由を必要としてしまうこと」。
何か新しいことを始めたいのに、
「意味がないとダメ」
「誰かと一緒じゃないとダメ」
と思ってしまう制限です。
広告では、「楽しむことに理由はいらない」「今この瞬間に、自分の人生を少し豊かにしていい」と言葉を添えることで、読者の背中をそっと押せます。
商品の役割
商品やサービスは、
「自分を解放し、人生の色を増やすきっかけ」
です。
つまり、
非日常を提供する手段ではなく、
心の再起動ボタンとして描くのが効果的です。
たとえば:
・陶芸体験なら「無心になれる時間を取り戻す装置」
・キャンプ体験なら「日常から距離を置き、本当の自分と対話できる時間」
・旅行サービスなら「思い出を作ること以上に、“何も考えない時間”をくれる存在」
このように、
「結果」ではなく
「体験そのものに意味がある」と表現します。
使うことで想像できる未来
・週末が“回復の時間”に変わり、平日の集中力が上がった
・「またやりたい」と思える趣味ができて、自分の時間が楽しみになった
・体験中、久しぶりに“時間を忘れる”感覚を思い出した
・「何もしていない自分」を責める時間がなくなり、満たされるようになった
未来を
「何かを得ること」ではなく、
「感じることが変わる」として描写するのがコツです。
得られるベネフィット
・やるべきことから離れたやってもいいことを取り戻せる
・「どうせ自分には…」という思考から解放される
・子どもやパートナーのこと以外に、自分のための話題ができる
・趣味ができたことで、会話やSNSでの表現にも明るさが戻る
この分野では、ベネフィットを“人間関係”や“自己認識の変化”まで広げると、より響きやすくなります。
使ったことでどのように変われるか
・「どうせ何も変わらない」と思っていた日常に、小さな変化を起こせるようになった
・自分にとって何が心地いいか、何が楽しいかが分かるようになった
・何かに夢中になることが、こんなに心を軽くしてくれるとは思わなかった
・「これをやってる時間の自分、好きかも」と初めて思えた
変化の本質は、
「生活の主導権を少しだけ自分に戻すこと」。
それができた瞬間から、
自己肯定感がゆっくりと回復していきます。
応用のアドバイス
このジャンルでは、
「イベント内容」や「体験のスケジュール」ではなく、
「なぜこれを体験すべきなのか」「体験後、どう感じられるようになるのか」が鍵になります。
大切なのは、
読者が「自分に許可を出せるようになること」。
ですので、
・“自分のための時間”を肯定する言葉
・“結果よりもプロセスが大切”だと伝える構成
・はじめの一歩のハードルが低いことを強調する工夫
この3つが整えば、
「やってみたいけど迷っている層」
が一気に動きます。
このように、
趣味・体験・レジャー系の広告は、
「新しい挑戦」や「楽しい時間」を売るのではなく、
「本来の自分を思い出すきっかけ」としてストーリー化することで、
多くの共感と申し込みを引き出すことができます。