- 「Real The Value」が刺さる理由
- 溝口勇児氏
- 堀江貴文氏
- 三崎優太氏
- 番組内に“いそうな起業家の物語”で読み解く、リアル用語辞典
- 【1minute 1st Pitch】
- 【SELF VALUATION】
- 【First Impression】
- 【3minutes 2nd Pitch】
- 【パワハラタイム】
- 【HELPカード】
- 【バリューアッププラン】
- 【REAL VALUATION】
- 【最終ジャッジ】
- 【司会】
- 【ENDING】
- あなたの事業、何点ですか?
- 「良いアイデア」と「通用する事業」の決定的な違い
- “プロの質問力”を盗め!事業ヒアリングでわかる5つの論点
- 失敗事例から学べ!価値を見誤ったビジネスの共通点
- アイデアを“スケール”させるロードマップの描き方
- この視点があれば、あなたも“価値を見抜く人”になれる
「Real The Value」が刺さる理由
ただのビジネス番組じゃない!“価値の本質”に切り込むリアルな会話の魅力とは?
起業に興味がある人。
副業を探している人。
ビジネスを始めてみたけれど、どこか壁にぶつかっている人。
あるいは、「世の中で“売れる事業”って結局何が違うの?」と疑問を抱いているすべての人にこそ見てほしいのが――
YouTube番組『Real The Value』です。
この番組、ただのビジネス談義ではありません。
出てくる話はすべて「リアル」。
夢物語でも、キラキラ経営者の自慢話でもない。
語られるのは、今この瞬間に実際に動いている事業の裏側、そしてその“リアルな価値”とは何なのか?という超本質的な問いかけです。
なぜ、面白いのか?
『Real The Value』では、実際に起業家が自らの事業アイデアをプレゼンし、それを聞いた3人のチェアマン(いわば“目利きのプロたち”)が、
「それ、本当に価値あるの?」
「どこで差別化してるの?」
「これ、スケールする?」
という鋭い視点でズバズバと核心を突いていくスタイルが特徴です。
テレビのような演出過剰な編集はなく、かといって退屈でもない。
むしろ、まるで隣で一緒に経営会議を聞いているかのような没入感があります。
ただ“見る”だけで終わらない、学びの宝庫
この番組のすごいところは、
「ビジネスの勉強」
になるのはもちろん、
“自分自身の視点”が鍛えられることにあります。
たとえば、登場する起業家のアイデアを聞きながらこう考えてみてください:
-
このサービス、本当にニーズある?自分なら使う?
-
強みは何?他とどう違う?
-
スケールする?収益構造は?
-
ボトルネックは?資金?人材?仕組み?
…そう、これってビジネスフレームワークの訓練そのものなんです。
3C分析やバリュープロポジション、
PMF、LTV、CAC…こうした理論を学ぶより前に、
“考え方”そのものを身につける体感型の学びがあるのです。
視聴の仕方で、学びは100倍変わる
「面白そうだから流し見する」
……それだけでも価値はあるかもしれません。
ですが、視点を少し変えるだけで得られる学びは爆増します。
おすすめの見方は、以下の3ステップ:
-
起業家のプレゼンを聞いて、自分で評価してみる
-
事業の強みは?どこに課題がある?と仮説を立てる。
-
-
チェアマンたちの意見と自分の考えを比べてみる
-
「なるほど、そこか!」と納得したり、
「あれ、そこ見てなかった…」と気づいたり。
-
-
実際のビジネスに当てはめて考えてみる
-
自分の仕事・副業・商品企画にも応用可能。
意外と“他人の失敗”が一番学びになる。
-
起業しなくても“価値を見抜く力”は一生モノ
「私は起業するつもりはないから…」という方にも声を大にして伝えたい。
この番組で得られる“価値を見極める力”は、ビジネスに限らず、
日常のあらゆる場面に応用できます。
目の前の情報が本当に正しいか?
SNSでバズっている商品は、本当に必要なのか?
自分のアイデア、独りよがりになっていないか?
私たちは日々「価値を選ぶ」場面に直面しています。
だからこそ、
“価値の眼”を持つことは、すべての人にとっての武器になるのです。
そして次は——
では、この“価値の本質”に迫る番組の中で、視聴者の心を掴んで離さないのが、3人のチェアマンたち。
彼らの圧倒的な実績と、
その言葉の裏にある経験知があるからこそ、この番組は本物になる。
次回は、その3人の素顔と実績に迫ります。
“なぜ、彼らの言葉が刺さるのか?”
その理由を知れば、
『Real The Value』の見え方は、
もうまったく変わります——。
溝口勇児氏
“筋肉”と“思想”を兼ね備えた稀有な実業家
『Real The Value』という番組を語るうえで、
溝口勇児という存在は欠かせない。
一見すると、筋肉質でエネルギッシュな印象が前に出がちな人物だが、
その発言に耳を傾けていくと、そこには事業の本質を射抜く洞察力と、
極めて冷静かつ理論的な“観察者の目”があることに気づく。
彼は、フィットネス業界にテクノロジーを掛け合わせた
「FiNC(フィンク)」を立ち上げ、
ヘルスケア×テックの領域を牽引してきた先駆者でもある。
過去の資金調達: 2018年には累計100億円以上の資金調達を実施しています。
資金調達や組織づくり、
スケール戦略など、FiNCを通して彼が体得してきた経営ノウハウは、
番組内でも随所に活かされている。
そして、
もう一つ彼を語るうえで欠かせないのが格闘技との深い関わりである。
溝口氏は、自身も長年格闘技に親しみ、
ブシロード傘下の「RIZIN」や、格闘家・朝倉未来氏との関わりを通して、舞台裏から日本の格闘技界に貢献してきた人物だ。
実際に
「BreakingDown」や「朝倉未来1年チャレンジ」
といったプロジェクトにプロデューサーとして関わる中で、
ただのスポンサーやパトロンではなく、
「選手の人生に介入し、成長をプロデュースする」
ような存在でもあった。
この経験が、
彼の人間観察力や事業家への洞察力にもつながっている。
格闘家の“勝つ理由”と“負ける理由”は紙一重。
その見極めを支えるのは、技術や努力だけではなく、
「この人はなぜ戦うのか」という深層心理への理解だ。
溝口氏が『Real The Value』で語るビジネス分析も、
この格闘技的な「人を見抜く目」に裏打ちされている。
彼が事業アイデアを聞くとき、
単に目先の儲けやマーケットの話だけで評価を下すことはない。
必ず
「社会にとってこのサービスはどんな価値を持つのか」
「ユーザーはこのプロダクトによって何から解放されるのか」
という視点がセットで語られる。
たとえば、
あるゲストが出した事業案に対して
「その課題って、わざわざあなたのサービスを使わなくても、すでに他の方法で解決できてませんか?」
と問いかけたシーンがある。
これは、単なる粗探しではなく、
課題の“本質”とその“切実度”を見極めようとする、
彼ならではの鋭さである。
このような問いができるのは、
彼自身が
「自分のサービスで世界を少しでも変える」
ことに真剣に向き合ってきた当事者だからこそだ。
さらに注目すべきは、
彼の事業分析における“地に足のついたスケール思考”だ。
実際、彼が投資家として関わるプロジェクトも多く、
成長ステージにおける資金戦略やマーケット選定、
出口戦略への視点も非常に具体的で、現実的である。
事業に夢を描く一方で、
それをどうやって形にしていくかという“冷徹な実行力”を重視する点が、
他のビジョナリーとは一線を画す所以だ。
番組内でもたびたび見られるのが、
「理想は分かる。で、誰がどのようにお金を払うのか?」という問い。
これは、
いわば彼の信条でもある「理想と現実の橋渡し」を体現する質問だ。
多くの起業家がビジョンに熱くなりすぎて足元の戦略を見失いがちな中で、溝口氏は一貫して「構造」と「数字」でビジネスを語る。
また、
溝口氏のもう一つの顔として、
「思想を持った経営者」
である点も見逃せない。
事業の目的を語る際、彼は“自分が何のためにこの事業をやるのか”を明確に言語化することの重要性を説く。
たとえば
「健康とは、ただの筋トレやダイエットの話ではない。人が本当に自由に、幸福に生きるための基盤である」
という彼の言葉には、
単なるフィットネス事業を超えた“思想”が込められている。
このような思想と論理の両輪を持ち合わせているからこそ、
彼のフィードバックには一貫性があり、聞く者に強い納得感を与える。
単に
「言いにくいことをズバズバ言うチェアマン」
ではなく、
「本気で世の中を変えようとする人たちに、本気で向き合う人物」
なのである。
一方で、
彼は若い起業家に対して厳しい視線を持ちながらも、
情熱がある者にはとことん寄り添う姿勢も見せる。
番組を見ていると、
どこか「理想の先輩」的な立ち位置にも感じられることがある。
これはおそらく、
彼自身が若い頃に苦労しながら事業を立ち上げた過去を持ち、
試行錯誤を繰り返してきたからこそ、
他人の“挑戦”に対して敬意を払っている証だろう。
『Real The Value』を通して溝口氏のコメントを聞いていると、
ただビジネスを評価しているのではなく、
「人間そのもの」を見ているような印象を受ける。
それは、事業が成功するか否かを最終的に決めるのは、
アイデアの良し悪しではなく、
“誰がやるか”であるという、
彼なりの信念が背景にあるからだ。
そして、
視聴者にとって最大の価値は、
その視点を“学べる”ことにある。
彼のフィードバックを追体験することによって、
視聴者は
「なぜこの事業は刺さらないのか?」
「どうすれば価値を高められるのか?」
という分析的な視点を養うことができる。
これは、
単に番組を楽しむだけでなく、
自分自身が将来、事業を立ち上げたり、
提案を通したりするときに役立つ“思考のフレーム”となっていく。
『Real The Value』の見どころは数あれど、
溝口勇児という男の存在は、
間違いなくその核心のひとつだ。
理想に燃え、現実を見据え、思想を持ち、数字で語る。
彼の一言一言に耳を傾けることは、
あなた自身のビジネス感覚を“リアルに”鍛える時間となるだろう。
堀江貴文氏
――未来を読み切る男の「越えない一線」
ビジネス番組『Real The Value』を観るとき、
視聴者の多くが自然と注目するのが堀江貴文(ホリエモン)氏だ。
時に大胆で、時に辛辣な物言い。
それでもなお、多くの人が彼の意見を「聞きたい」と思うのはなぜか。
それは彼が、単なる実業家でも、評論家でもない、
“未来を常に読み続けてきた男”だからだ。
彼の発言には、常に「5年後、10年後を見据えた構想」がある。
インターネットがまだ“パソコン通信”と呼ばれていた時代に、
その可能性に気づき、ライブドアを通してネットの民主化を押し進めた。
テレビとインターネットの融合、
SNSの到来、YouTubeの影響力、宇宙開発、モバイル事業、サブスク、個人の時代——彼が語ってきた「未来」は、気づけばすべて“現在”になっている。
言葉に力があるのは、その背景に「実践してきた結果」があるからだ。
彼は未来を語るだけではない。
自ら動き、形にし、世の中を変えてきた当事者である。
たとえば宇宙事業「インターステラテクノロジズ」、
和牛のサブスク「WAGYUMAFIA」、
格安SIM「ホリエモバイル」など、
分野の垣根を超えたプロジェクトに常に手を出しながら、
それぞれに本質的な問題意識をもって取り組んでいる。
その一方で、彼の過去には「逮捕」という劇的な出来事がある。
2006年、証券取引法違反の疑いで逮捕・起訴され、実刑判決を受けた。
この経験によって、彼は「一線を超えることのリスク」を、
誰よりも深く理解した人物になった。
だからこそ、
現在の堀江氏にはある種の“絶対に踏み込まない領域”がある。
それは、「法律に対する徹底した理解と尊重」だ。
過激な発言をする一方で、彼は明確に“リスクの線引き”をしている。
「警察に聞いて“問題ない”って言われても、裁判では負けることがある。つまり、口頭確認は担保にならない。」
この言葉は、
法律における“OK”の定義が、実務と法廷ではまったく異なる
という現実を突いている。
ここで彼が紹介した方法がある。それが――
ノーアクションレター制度(No-Action Letter)
この制度は、
金融庁などの行政機関が
「こういうスキームで事業を行おうとしているが、法律に触れるのか?」
という問い合わせに対して、
「現時点では法令違反としない(=違反の疑いがあっても、行政処分等の“アクション”は取らない)」という
“事前確認的な返答”を公に発行してくれる仕組みである。
たとえば以下のようなビジネスモデルに有効だ。
-
フィンテック関連で金商法や資金決済法に関わるもの
-
ヘルスケアサービスで薬機法や医師法との関係が懸念されるケース
-
サブスクモデルや暗号資産を組み込んだ新規スキーム
もちろんこれは免罪符ではないが、
法的グレーをクリアにする「担保の一つ」として非常に有効だ。
堀江氏が強調するのは、「グレーを攻めない」のではない。
「グレーと認識しているのなら、まず正体を確認してから進め」
という姿勢だ。
それが、口約束ではなく、
行政機関や法律専門家による“文書による確認”であるべきなのは
言うまでもない。
こうした動きを取るスタートアップが、
実際に堀江氏からも評価されている。
「ここまで準備してるならいいね」といった一言の裏には、単に面白いかどうかではなく、“実行可能性の高さ”=事業の現実性を見ているのである。
だからこそ、
彼は「勢いだけのスタートアップ」に厳しい。
アイデアが良くても、
「その仕組み、ノーアクションレター取ったの?」
という問いが出た時に答えられなければ、その段階でアウトだ。
この“質問”が投げられること自体が、堀江氏ならではの視点である。
だからこそ、堀江氏の発言には重みと説得力がある。
それは単なる知識やデータではなく、実際にリスクを負い、
自由を奪われた経験に裏付けられているからだ。
また、彼のもう一つの魅力は、
常に“本質”を突く姿勢である。
アイデアを聞いて「面白いね」と口では言いつつも、表情は動かない。
その裏で、彼は常に
「それは誰の課題を、どう解決しているのか?」
「それ、本当にスケールするの?」
という視点で事業を見ている。
たとえば、
派手なマーケティングや目新しさでごまかそうとする起業家には手厳しい。
「それって、結局広告でゴリ押しするビジネスでしょ?続かないよ」と、
静かに突き放す。
その視線は冷たいようでいて、
実は本当に価値のあるものを作ってほしいという願いの裏返しだ。
だから、
彼の厳しい言葉には、多くの起業家が
「悔しいけど納得した」
と感じるのである。
堀江貴文という人物は、
突飛でエキセントリックなキャラに見えて、
実は非常に繊細で論理的な“知性の塊”だ。
彼が番組で発する一言一言には、
未来への確信と、過去から学んだ慎重さの両方が詰まっている。
『Real The Value』における彼の存在は、
まさに“未来を読むリアリスト”であり、
希望と警告を同時に届けてくれる貴重なフィルターである。
この視点を持って番組を見れば、
堀江氏の発言が“刺激”ではなく、“指南書”に変わる。
彼が「いいね」と言ったアイデアには理由があり、
「これは厳しい」と言った裏にも、
膨大な経験知が宿っているのだ。
三崎優太氏
――“失敗”すらプロモーションに変える青汁王子の真骨頂
『Real The Value』
に登場する3人のチェアマンの中で、
最も“現代的”な成功者といえるのが、
三崎優太氏(通称:青汁王子)だ。
その存在は、型破りで、破天荒で、そしてどこか人間臭い。
だが、
彼のキャリアを追うと見えてくるのは、
自己ブランディングと
ビジネス構築の天才的バランス感覚
である。
彼が最初に注目を集めたのは、
20代で青汁通販ビジネスを立ち上げ、
年商100億円を突破するなど若くして成功を収めた頃だ。
彼は、時代の波に乗るだけでなく、
波を自ら起こす存在として、早くからビジネス界の表舞台に立った。
だが、その後、法人税法違反による逮捕・・・
成功者から一転、世間から「転落」のレッテルを貼られることとなる。
だが、ここで終わらないのが三崎氏の真骨頂だった。
「青汁王子」というキャラクターを前面に打ち出し、
YouTube、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokといった各種SNSで
自らの“失敗と復活”を語り続けた。
最近では株式の信用取引での失敗を経て、
「青汁王子」から「三崎優太」として
インフルエンサーから経営者として歩みだすことに。
現在、
彼はバイクメーカーの経営や不動産事業、エンタメ事業など多岐にわたるプロジェクトを同時並行で展開している。
番組での立ち位置は、ただの“突っ込み役”ではない
三崎氏のフィードバックは、時に辛辣で、時に感情的にも見える。
しかしその言葉の裏には、
彼自身が
“何度も失敗と再起を繰り返してきた経験”と、
“市場で商品を売り続けてきた現場感覚”がある。
『Real The Value』
に登場するスタートアップの多くは、
ビジネス書や講座で学んだ「型」に則ってプレゼンを行う。
しかし、
三崎氏はその型に頼った表面的な話にすぐ気づく。
鋭い質問が飛ぶたびに、
プレゼンターの緊張は高まり、
視聴者は“本質に触れた”瞬間を感じることになる。
三崎氏は、
他のチェアマンのように、
分析的に数字を読み解いたり、
フレームワークで整理することもできるが、
最大の魅力は、
「その場の空気を切り裂くリアルな感覚」
で話す点にある。
『Real The Value』で三崎優太を見る意味
この番組で三崎氏の発言に注目することは、
“リアルに価値を生み出せる人間の視点”を学ぶことに等しい。
「好き嫌いは分かれる。でも、この人の言うことは、一度ちゃんと考えた方がいい。」
それが、いま『Real The Value』という番組を観る視聴者たちの共通認識になっている。
番組内に“いそうな起業家の物語”で読み解く、リアル用語辞典
これは空想の物語です。。。
【1minute 1st Pitch】
「こんにちは、市川ユリ、28歳です。」
声のトーンは穏やかだが、明らかに緊張している。
けれど、彼女の目は一度も伏せられず、まっすぐ前を見据えていた。
手元の資料に目を落とすことなく、彼女は口を開いた。
「私は、オリジナルキャラクター“ヒメ”を軸にしたスキンケアブランドを立ち上げました。
このキャラは、私自身の“孤独な青春”から生まれたものです。」
彼女が手元のリモコンを押すと、背後のスクリーンに一枚のビジュアルが現れる。
ふんわりとした色彩、柔らかく微笑む猫耳の少女――“ヒメ”がそこにいた。
「“推し”がそばにいるような体験を、日常に届けたい。
それがこのブランドの原点です。
メイクやスキンケアが“義務”ではなく、“物語とつながる時間”になってほしいんです。」
一瞬の静寂。その直後、チェアマンたちが口を開き始める。
【堀江貴文】
「つまり……アニメキャラ×化粧品ってこと?
どっちが主役なんだろうって、ちょっとわかりづらいね。」
【三崎優太】
「うーん…“エンタメを肌で感じる”ってのは、キャッチーだけど、
これって“売るもの”が化粧品なの? それともキャラなの?」
【溝口勇児】
「そもそも、こういうIP(知的財産)ビジネスって、熱が冷めると一気に売上落ちるんだけど。
それをどう超えるつもり?」
【南原竜樹】
「でも世界観は伝わった。
キャラクターを“商品じゃなく関係性”として届けるなら、可能性はある。」
【柴田陽子】
「言葉のチョイスがすごく優しいね。“照らす存在”って表現に引っかかりを感じた。
もう少し、ターゲットのイメージが明確に見えると嬉しいな。」
市川は、微かに頷きながら耳を傾ける。
緊張しつつも、どこか嬉しそうな顔をしていた。
彼女にとってこれは「叩かれる場所」ではなく、「伝えるために立った場所」なのだ。
【SELF VALUATION】
「企業評価は――1億円です。」
その言葉が落ちた瞬間、スタジオの空気がすっと静かになる。
全員が、口には出さずとも「その根拠は?」と心の中で問いかけた。
最初に動いたのは三崎優太。
口角を上げながら、しかし視線はまっすぐだ。
【三崎優太】
「キャラコスメの世界に、1億の価値ね。……まあ、面白いっちゃ面白い。
ただ、売上規模から見て“ちょっと盛ってる感”はあるかな?」
市川ユリ
「現在、月商は約680万円です。
初月の売上は580万円、そこから定期購入率を少しずつ上げてきています。
利益率は70%前後。D2Cで展開しているので、物流からCSまですべて自社内で管理しています。」
【堀江貴文】
「じゃあその1億って、どういう計算で出してる?
数字だけ見たら、5000万評価でも納得する人は多いと思うけど。」
市川は、少し呼吸を整えた後、静かに答える。
「現在のLTV(顧客生涯価値)は、約9,800円です。
これは、現時点での実績に基づいた数字です。」
※LTVとは、1人の顧客が生涯でそのブランドにどれだけお金を使うかの指標。
通常、初回購入金額に加え、リピート購入の回数・頻度をもとに算出される。
事業初期では“現時点での平均値”+“今後の予測”の両方を考慮するのが一般的。
市川は続ける。
「この9,800円というのは、まだ定期購入開始から半年の実績に基づいています。
現在、継続率は約28%。
ここから12ヶ月まで継続した場合、1人あたり1万5,000円を超える見込みです。」
【溝口勇児】
「つまり、現時点では9,800円だけど、それはまだ“途中経過”であって、
君の中ではLTV=売上ポテンシャルと見て評価してる、ってことだね。」
市川は、しっかりと頷いた。
「はい。私は、“数字を盛る”のではなく、
“伸びる根拠を持って見ている数字”として、LTVを評価に織り込んでいます。」
【柴田陽子】
「リアルな見立てって感じね。
“今の数字”と“未来の数字”をちゃんと分けて話してくれるのは好感が持てるわ。」
【南原竜樹】
「でもね、“構造として積み上がる”って判断できなきゃ、
いくら夢を語っても投資はつかない。
そのあたり、君の“ファンの育て方”に期待してるよ。」
司会がタイミングを見て促す。
「それでは、First Impression――チェアマンの皆さん、札をお上げください。」
【First Impression】
司会の一言で、一斉にチェアマンたちの札が上がる。
FAKE:4名/REAL:8名
FAKEが予想より多く、空気にややざわつきが走る。
【司会】
「それでは、評価の理由を伺っていきます。」
【堀江貴文】
「キャラクタービジネスって、熱狂は生まれやすい。SNSで一気に拡散されて“ドカン”と売れることもある。
でも、正直、冷めるのも早い。賞味期限が短いんだよね。」
堀江が指を立てながら続ける。
「それに、IP(知的財産)頼みのモデルって、基本“他人の土俵”で相撲取ってるわけ。
ライセンスの契約条件ひとつで売り方も収益も変わる。それ、想定してる?」
※IP(Intellectual Property)は、キャラクターやブランドなどの知的財産。
利用には契約が必要で、条件次第でビジネスの自由度や利益率に直結する。
【市川ユリ】
「おっしゃる通りです。
ただ、私たちの“ヒメ”は自社開発の完全オリジナルIPで、
第三者の許諾なしで、世界観を自由に展開できる状態です。」
【溝口勇児】
「今の話、気持ちはすごく伝わってる。
でもね、僕らが見たいのは“感情”と“構造”のバランスなんだよ。」
彼は資料に目を落としながらつぶやくように言う。
「今この段階での評価額――1億円。
数字的には出てたけど、そこに“再現性”と“スケーラビリティ”があるかどうか。
それをこの後の説明で確認したい。」
※スケーラビリティとは、事業がどこまで“拡張可能”かを示す概念。
売上が増えても仕組みが崩れないことが重要な評価ポイントになる。
【三崎優太】
「個人的には、めっちゃ刺さってるよ。
キャラの表情、言葉の選び方、SNS設計――細かいところに感性がある。」
少し間を置いて、冗談めかして続けた。
「でもさ、LTVがまだ1万円未満で、月商600万ちょっとでしょ?
なのに1億の評価って聞くと……うーん、ちょっと背伸びしてる感はあるよね。」
【市川ユリ】
「評価額は、現時点の売上だけではなく、
キャラクターの展開性――アニメ化、書籍、コラボブランドの複線、
さらにSNSでの“感情資産”を含めて算出しています。」
【柴田陽子】
「“感情資産”、いい表現ね。
確かに、“語りたくなる世界観”って、リピートの源になると思う。」
※リピート率が高い=LTVが自然と上がる構造を作れる。
LTVは、顧客の購入金額×購入頻度×継続期間で決まり、体験価値と密接にリンクする。
【南原竜樹】
「ただ一点。
このビジネスが1年後も2年後も通用するためには、“世界観”だけじゃ足りない。
数字で“構造”を見せてくれなきゃ、俺はまだリアルとは言い切れない。」
市川は小さく息を吸って、真顔でうなずいた。
プレゼンの手元資料を持ち直し、画面切り替えの準備に入る。
【3minutes 2nd Pitch】
――“想い”だけじゃ、戦えない。ここからは数字と構造の時間。
市川がスライドのページを切り替えると、
画面には「マーケット・構造・戦略」
という3つのキーワードが浮かび上がった。
市川ユリ
「まず市場についてご説明します。
国内のフェイスケア市場は年間約3,400億円。
その中でも、
10代~30代女性をターゲットにした“キャラクターコラボ系コスメ”は、
いわばブルーオーシャン
――競合が少なく、ブランドの“物語性”が武器になります。」
※ブルーオーシャンとは、競争が激しい“レッドオーシャン”ではなく、未開拓・独自性のある市場領域のこと。
小さくても“ファンの熱量”が高いジャンルに参入すると、一気にポジションを確立できる。
「うちは現在、完全自社開発のキャラクター“ヒメ”を使った
フェイスマスクと化粧水を販売しており、EC経由のD2Cモデルで展開しています。
店舗を持たない分、利益率は約70%、在庫管理も月2回の少量発注でリスクを抑えています。」
※D2C(Direct to Consumer)=中間業者を省き、自社ECなどで直接顧客に販売するモデル。
ブランド力と利益率を自社でコントロールできるのが強み。
「現在の月商は約680万円。
初回購入者のうち、28%が定期購入に移行しています。
この継続率をもとに、LTVの現時点推計は約9,800円。
今後12ヶ月時点で、平均LTVは15,000円超になると見込んでいます。」
市川が自信を持って言い切ると、三崎の眉がわずかに動いた。
【三崎優太】
「数字はクリアだね。LTVが伸びる構造も理解できる。
でも……ここが一番大事なとこなんだけど――
“誰が買ってる”のか、見えてる?」
市川ユリ
「はい。初回購入者のうち約72%が、
“SNSでヒメの投稿を見て気になった”と回答しています。
属性は、Z世代と呼ばれる10代後半~20代後半の女性が中心。
ただし、最近は“推しと一緒に使える”という理由で、
カップル購入やギフト需要も増えてきています。」
【堀江貴文】
「つまり、買ってるのは“モノ”じゃなくて“関係性”なんだな。
それをどう再現性のある仕組みにするか、そこが一番難しい。」
市川ユリ
「その点では、私たちが今重視しているのがCVR(コンバージョン率)の改善です。
現在、広告からのCVRは3.2%。
Instagramでのリール投稿を見たユーザーが、
“ヒメの1日”に感情移入し、そのまま商品を購入しています。」
※CVRとは、広告を見たユーザーが実際に商品を買った割合。
2〜3%あれば優秀とされるなかで、3.2%はかなり良好な数値。
「また、CPM(広告1,000回あたりの表示コスト)は平均280円で、
広告効率も比較的良好なため、CPAは2,600円に抑えられています。」
※CPA(顧客獲得単価)は、1人の顧客を獲得するのにかかった広告費。
LTVとのバランスが重要で、LTV > CPAであれば、利益構造が成り立つ。
市川が語るたびに、チェアマンたちの手元の資料に目が走る。
数字だけを聞けば確かに悪くない
――けれど、この構造が「本物」かどうか、
その判断はまだ下っていない。
【南原竜樹】
「ヒメの世界観、キャッチーだし魅力はある。
でも“継続性”がどこまで担保されてるか、もう少し深掘りたい。
アニメ化の話、出てたよね?」
市川ユリ
「はい。現在、Instagramフォロワーの反応をもとに、
“ヒメの短編アニメ企画”が動いています。
実現すれば、コスメとの連動だけでなく、
“ヒメの物語”自体がユーザーの生活導線に入る。
それが私たちのバリューアップの起点になると考えています。」
【溝口勇児】
「よし……なるほど。
数字と世界観がかみ合ってる。
でも次は、“ヒメがいなくなったとき、君の事業は残るのか”――
そこまで踏み込んで考えてるか、聞きたい。」
市川の背筋がぴんと伸びた。
彼女の中で、何かが切り替わったように見えた。
【司会】
「それでは、ここからは“パワハラタイム”に入ります。
チェアマンたちが、本音で“覚悟”と“本質”を問う時間です。」
【パワハラタイム】
――ここから先は、武装も演出も通用しない。
“事業”ではなく“覚悟”を見られる時間。
チェアマン席のライトが少しだけ強くなる。
対して、ステージ中央の照明はやや暗くなり、
スポットライトが市川ひとりを照らす。
空気が変わったのを、誰もが感じた。
【堀江貴文】
「じゃあ聞くけどさ――
もし“ヒメ”が思ったよりバズらなかったら?
数字が落ちて、再生回数もリーチも止まったら、君は何を武器にするの?」
市川は一拍置いて、ゆっくりと答えた。
「私は、ヒメがただのキャラクターだと思っていません。
彼女は“言葉にできなかった想い”の代弁者で、
スキンケアを“感情とつながる儀式”に変える存在です。」
少し、息が熱を帯びる。
「たとえ数字が出なくても、“世界観で買ってくれた”人たちがいます。
私はその人たちの信頼に応えたい。
だから、ヒメが静かになっても、“信頼の設計図”だけは絶対に壊れません。」
※信頼の設計図とは、LTVやCVRの裏にある“ユーザーの感情フロー”のこと。
数字だけでなく、「どういう心理の動きで、リピートや推奨につながっているか」を指す。
【溝口勇児】
「でも、D2Cって“熱量ビジネス”だよね?
つまり“今”の熱が消えたら終わり
――そのリスク、どう折り合いつけてるの?」
市川の目が強くなる。
「だからこそ、私は“エンゲージメント指標”を常に追っています。
数字だけでなく、1つの投稿に何人が共感してくれて、
どれだけのUGCが生まれたかを“次の打ち手”にしています。」
※エンゲージメント指標とは、フォロワーの数ではなく、“どれだけアクション(いいね・コメント・シェア)してくれたか”を示す数字。
本当の熱量はフォロワー数ではなく、この指標に現れる。
【三崎優太】
「じゃあ、君が事業で一番大事にしてるKPIは何?」
「はい。売上でもLTVでもありません。
私が一番追っているのは――“語られ率”です。」
静寂が一瞬スタジオを包む。
「ユーザーが“ヒメ”をどう紹介しているか、どんな言葉でシェアしてくれているか。
それが“ブランドの真実”だと思っています。」
【柴田陽子】
「語られ率、いいわね……それ、どこで追ってるの?」
「Instagramの保存数、メンション率、DMのシェア回数です。
そこに載った言葉と温度を“次の設計”に活かしています。
ヒメという存在を、毎日の“呼吸”みたいに思ってくれる人を増やしたいんです。」
【南原竜樹】
「……じゃあ最後に聞こう。
今ここに、全部の在庫が余って、社員が辞めて、
売上がゼロになったとしても――君はこの事業を続ける?」
静まり返るスタジオ。市川は一歩前に出る。
「はい。私は“売れるかどうか”じゃなく、“届けたいかどうか”でこの事業を選びました。」
「ヒメがいたから、私は救われた。
今度はヒメが、誰かを救えるかもしれない。
その未来を見たいから、私は、続けます。」
一瞬の沈黙のあと、チェアマン席に微かなざわめきが生まれる。
柴田がうつむいたまま、笑った。
三崎は、腕を組んだまま少し目を細める。
堀江は、何も言わずに資料に目を落とすが、口元だけがゆるんでいた。
【司会】
「では続いて、HELPカードを使うかどうかの判断に入ります。」
【HELPカード】
――プロの一言で、戦局は一変する。
市川の口元に、はっきりとした決意がにじむ。
市川が手を伸ばす。
「……使います。HELPカード。」
指名されたのは、
SNSブランディングとコンテンツ戦略の第一人者、田嶋カナ。
元コスメ企業のCMO(最高マーケティング責任者)、
現在はD2Cブランドの立ち上げ支援を行う敏腕マーケターだ。
スタジオに入ってきた田嶋は、即座にスライドを一枚表示。
【田嶋カナ(HELP支援者)】
「正直、このブランド、可能性はある。
でも、まだ“熱狂の仕掛け”が足りない。」
会場がざわつく。
「市川さんのプレゼンで感じたのは、
“熱意”はある。でも、リピーター設計の核心がまだあいまい。」
※リピーター設計とは、一度買ってくれた人を“継続顧客”に転換する導線のこと。
LTVを上げるために必要不可欠な、D2Cの心臓部分。
「たとえば、ジャーニーマップを作ってますか?」
【市川ユリ】
「はい。現状は、
SNS → 商品購入 → 継続定期 という3ステップで設計しています。」
【田嶋】
「それ、ジャーニーの“線”じゃなくて“点”です。
ユーザーは感情で動く。
“ヒメと過ごす朝のルーティン”を共有するイベント、
“ヒメの誕生日”に限定アイテムを出す。
そういう感情の波を、プロダクトタイミングに組み込むのが次のステージです。」
※カスタマージャーニーとは、ユーザーが商品を知り、買い、使い続けるまでの感情の流れを可視化したもの。
D2Cでは「購入後の体験設計」まで含めて戦略を組む必要がある。
【三崎優太】
「つまり、感情で始まり、デザインで買って、ストーリーで続く。
それがこのビジネスの“正解ルート”ってことだね。」
【堀江貴文】
「んで、それを裏から支えるのがKPI設計だな。
何を追ってる? “商品売れた”だけじゃダメだよ。」
【田嶋】
「市川さんは、保存率、リピート率、平均継続月数、
そして私が提案したいのは、感情CTA率。」
チェアマンたちの表情が変わる。
※CTA(Call to Action)とは、“次の行動へ導く設計”のこと。
感情CTAとは、「投稿を読んで共感した」「泣いた」「誰かに教えたくなった」といった“感情起点の行動”の割合を指す。
【田嶋】
「感情CTAが上がれば、UGCも自然に増えるし、広告費も下がる。
つまり、CPAが勝手に下がってLTVが上がる構造ができるわけです。」
【溝口勇児】
「それができたら、1億評価は十分“REAL”だよね。」
【柴田陽子】
「むしろ、CPAやLTVじゃなく、
“共感偏差値”って考えた方がこのブランドには合ってるかも。」
【南原竜樹】
「おもしろい……なんか、事業から“人格”が見えてきたな。」
【田嶋】
「私からは以上です。
市川さんの“熱”と“体験設計”が交われば、
このブランドは“売れる”じゃなく、“続く”になります。」
拍手がわく中、市川は深く一礼をする。
助言のひとつひとつを、まるで自分の血肉にするように静かにうなずいた。
【司会】
「それでは、続いて【バリューアッププラン】へ進みます。
チェアマンの皆様からの、事業を“さらに高める提案”をお聞かせください。」
【バリューアッププラン】
――数字を超えて、“未来に残す価値”を創りに行く時間。
HELPカードによって“感情の構造”を強化された市川のプラン。
だが、ここで終わりではない。
チェアマンたちは、さらに“次の階層”を見ている。
【溝口勇児】
「このブランドには“推し活”という武器がある。
でもね――“推される”だけじゃ、続かないんだよ。」
市川が静かにうなずく。
「これから君がやるべきは、“コミュニティ設計”だ。
ヒメのファン同士が、“自分たちで価値を作れる仕組み”をつくる。」
※コミュニティ設計:ブランドを起点に、顧客同士がつながり、価値を共有・発信する仕組み。
成熟したD2Cブランドは、売り手と買い手ではなく、“ファンと共創者”の関係を築く。
「具体的には、NPS(ネットプロモータースコア)を追い始めた方がいい。
商品を使った人が“どれだけ他人に薦めたくなるか”――これが一番リアルな信頼の指標だ。」
※NPSとは、「あなたはこの商品を他人にすすめたいと思いますか?」という質問を通じて、ブランドの“ファン度”を数値化する指標。
高NPSのブランドは、広告よりクチコミで伸びる力が強い。
【柴田陽子】
「私からは、“生活導線に入る”っていう発想の深化を提案したいわ。」
「朝の洗顔、夜のケア……それだけじゃなく、たとえば“ポーチの中で旅するヒメ”、
“生理前のブルーな時期に寄り添うヒメ”みたいな、
ユーザーの感情カレンダーと連動した商品設計を作れると面白い。」
※感情カレンダーとは、ユーザーの“気持ちの動き”と“日常のタイミング”をマッピングするマーケティング手法。
商品の使用場面と感情をリンクさせることで、LTVが上がりやすくなる。
「つまり、“使う理由”を超えて、“そばにいてほしい理由”に変えていくの。」
【堀江貴文】
「いいね、それ。」
少しうなずいて、堀江が口を開く。
「……俺からはひとつだけ。
データを“見る”んじゃなく、“育てろ”ってこと。」
「君が集めてるKPI――CVR、CPA、LTV、エンゲージメント。
これ全部、“今の結果”でしかない。
だけど、そこから“未来の変化”を読み取れたときに、初めて経営になる。」
※経営におけるデータ活用とは、「現在地の把握」ではなく「成長のための意思決定」。
KPIを未来の仮説につなげられるかが、経営者の力。
「仮説と検証のPDCAを高速で回し続けられるか。
結局そこなんだよ。俺はそういう人が好きだし、君にはそれができる気がする。」
※PDCAとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Act(改善)の循環を回すマネジメント手法。
D2Cやスタートアップではこの“高速回転”が生命線となる。
【三崎優太】
「俺からはちょっと感情論かもだけど、言わせて。」
「……ここまで見てて思った。
このブランドは、ヒメじゃなく、君自身の物語が支えてる。」
「もしこの先、数字が下がっても、炎上しても、何かが壊れても
――“君の覚悟”が残る限り、ブランドは再生できる。
そういう意味で、“ヒメ”は“武器”であり、“君の鏡”でもあるんだよ。」
会場が静まり返る。
市川は一言も発さず、ただ静かに、何度も、深く頷いた。
【司会】
「それでは、最終評価――【REAL VALUATION】に移らせていただきます。」
【REAL VALUATION】
――これは、数字の評価ではない。
「今までと、これから」の全てを問う“覚悟の査定”。
司会の合図で、スクリーンの中央に大きな数字が浮かび上がる。
企業評価額:100,000,000円!
一瞬、空気が止まったような静寂。
チェアマンたちは無言のまま、表示された数字を見つめている。
市川の手が小さく震えているのがわかる。
けれど彼女は、下を向かない。
【司会】
「それでは、最終ジャッジに入ります。
この3人の判断が、クラブ入会の是非を決定します。」
ステージに緊張の風が走る。
【最終ジャッジ】
――溝口勇児:REAL
「最後まで、数字と真摯に向き合ってた。
あとは、仕組みの強化と再現性。そこさえ固まれば、
このブランドは“好き”という感情から、“続けたい”という習慣へ進化できる。」
――堀江貴文:REAL
「この場でプレゼンする人、たくさん見てきたけど……
“辞めない人”は、結局やり続ける。
数字だけじゃなく、“絶対にやる”って顔してた。」
――三崎優太:REAL
「……うん、これはもう、REALだよ。」
少し笑ったあとで、目だけは鋭く言葉を続ける。
「事業って、夢でもロマンでもなく、“地道な再構築の連続”だから。
その泥くささを、君はちゃんと受け入れてた。
そして、ヒメがいたからじゃなく――君だから、これはREALなんだ。」
【司会】
「3人のチェアマン、全員がREALを提示。
市川ユリさん、あなたは――Real The Value CLUB、入会決定です!」
拍手がわき起こる。
市川は両手で顔を覆い、泣きそうになりながら、何度も頭を下げた。
画面には、「REAL」の札が光る中、“ヒメ”の微笑むビジュアルが映し出されていた。
【ENDING】
事業に必要なのは、数字とロジックだけじゃない。
情熱、設計、覚悟、そして、“折れない理由”。
ヒメというキャラクターの背後にあったのは、
ひとりの起業家の「過去」と「祈り」だった。
そしてその祈りが、
今日、ビジネスとしての価値に変わった。
■ IP(Intellectual Property)
知的財産のこと。
キャラクター・ブランド名・デザイン・物語など、企業が独自に所有し価値を生む創作物を指します。
例:ポケモン、ディズニーのキャラクターなど。ビジネスでは“IPをどう育てるか”が収益化のカギになります。
■ LTV(Lifetime Value)
顧客生涯価値。
1人の顧客が“生涯で合計いくら使ってくれるか”を示す指標。
例えば、1人のお客様が毎月3,000円の商品を12ヶ月継続した場合、LTVは3,000円×12=36,000円となります。
※LTV > CPA になることで、ビジネスは黒字化できます。
■ CPA(Cost Per Acquisition)
顧客獲得単価。
1人の新規顧客を得るのに必要な広告費のことです。
たとえば、5万円の広告を出して20人が購入した場合、CPAは5万円÷20人=2,500円になります。
■ CVR(Conversion Rate)
コンバージョン率。
広告やサイトに訪れた人のうち、どれくらいの人が実際に「購入」や「申込」をしたかを表す割合です。
例:100人中3人が買ったなら、CVR=3%。
※2~3%で優秀とされる分野もあります。
■ D2C(Direct to Consumer)
メーカー直販モデル。
ブランドが自ら商品を製造・販売し、中間業者(問屋・小売店など)を通さず、直接顧客に届けるビジネス形態。
SNSや自社ECを活用してブランド世界観を直接届けられるのが特徴です。
■ CPM(Cost Per Mille)
広告1,000回表示あたりのコスト。
ネット広告の効率を測る基本指標のひとつ。
例:広告費1万円で広告が10,000回表示された場合、CPMは1,000円となります。
■ UGC(User Generated Content)
ユーザーが自発的に作るコンテンツ。
商品レビュー・SNS投稿・動画・ブログなど、企業ではなく“顧客自身が発信”する内容を指します。
UGCは信頼性が高く、広告より影響力を持つこともあります。
■ KPI(Key Performance Indicator)
重要業績評価指標。
「目標達成のために何を追いかけるか」を明確にするための数字。
例:売上・サイト訪問数・購入率・継続率など、目的に応じて設定されます。
■ NPS(Net Promoter Score)
ブランドの“推奨度”を測るスコア。
「あなたはこの商品・サービスを他人に勧めたいと思いますか?」という質問に対しての回答から、ブランドのロイヤリティ(ファン度合い)を測る方法です。
■ PDCA(Plan → Do → Check → Act)
ビジネス改善の基本サイクル。
-
計画(Plan)
-
実行(Do)
-
検証(Check)
-
改善(Act)
この4ステップをぐるぐる回し続けることで、事業を進化させていく考え方です。
あなたの事業、何点ですか?
『Real The Value』でプロが無意識に見ている“3つの視点”
ビジネスプランを聞いたとき、
堀江貴文、三崎優太、溝口勇児といったチェアマンたちが
「REAL」「FAKE」を瞬時に判断している場面があります。
彼らは一見感覚的に見えますが、実は非常に明確な評価軸を持っています。
その視点は、大きく分けて次の3つです。
1. 再現性
再現性とは、「この事業は、他の人がやっても、同じように成果が出るか?」という視点です。
「たまたまSNSでバズった」
「知人に頼んで売れた」
「特殊なスキルを持ってる自分だからできた」
といった要素は、評価においてはマイナスになることもあります。
なぜなら、
ビジネスとしての価値は「再現できる仕組み」にこそあるからです。
再現性があるというのは、
ノウハウが言語化されていたり、
誰がやっても一定の成果が出るように整っている状態です。
これはフランチャイズ展開や外注化を考えるときにも必要な視点です。
2. 拡張性
拡張性とは、
「この事業を10倍、100倍にしていくことができるか?」
という可能性の話です。
いくら収益が出ていても、
「自分ひとりの労働力」
に依存していたり、
「作業が属人化している」
と拡張はできません。
利益率が低すぎて、
売上が上がっても赤字になるようなモデルも
同様に評価されにくくなります。
拡張性のあるビジネスとは、
業務を仕組み化・自動化・外注化して、
売上が増えても負荷が爆発しない体制があることです。
また、
地域やターゲット層を広げたときに
通用する構造になっているかも問われます。
チェアマンたちは、「これは10倍にできるモデルか?」という観点から、
静かに、しかし鋭く見ています。
3. 継続性
継続性は、「この価値は、5年後も必要とされているか?」という問いです。
今だけ売れている“流行りもの”や、“一発屋”的なビジネスは、どれだけ短期で売上があっても評価されません。
例えば、
単発イベントや時流に乗ったSNS施策は、
売上こそ出せても再現や継続が難しい。
逆に、
「なぜ人はこれを何度も買うのか?」
「1年後も使い続けたくなる理由はあるか?」
といった部分に答えられると、
事業の厚みが一気に増します。
ここでよく使われるのが
「LTV(顧客生涯価値)」や
「継続率」などの数字です。
継続性の高い事業は、顧客の体験が“習慣”になっているのが特徴です。
事業の“リアルさ”は未来を描けるかどうかで決まる
どれだけ熱意があっても、
数字がよくても、
上の3つのうちどれかが欠けていると、
チェアマンたちは必ずそこを突いてきます。
逆に言えば、
この3つを明確に自分の言葉で語れるようになれば、
あなたの事業は「REAL」に近づきます。
再現性は、「仕組みにできているか」
拡張性は、「大きくできる設計か」
継続性は、「何度でも使われる理由があるか」
この3つを問い直すことで、
あなたのビジネスは
「想いのまま」から「戦略を持った事業」へと進化していきます。
次にREALを突きつけられるのは、あなたかもしれません。
「良いアイデア」と「通用する事業」の決定的な違い
――あなたの“面白い発想”、売れる準備はできていますか?
「このアイデア、面白くない?」
「こんなサービスがあったら便利だよね!」
「自分がほしいと思ったから、きっと他の人も欲しいはず!」
こうして生まれた“ひらめき”の多くが、
SNSに投稿され、ピッチイベントで語られ、
クラウドファンディングに挑戦します。
けれど、そのほとんどが続かない。
むしろ、最初の熱量がある分だけ、
うまくいかないときの落差は大きい。
では、何が違うのか?
結論から言えば、「良いアイデア」と「通用する事業」には、
明確な違いがあります。
その違いとは――“受け手視点で磨かれているかどうか”です。
「自分がいいと思うもの」から、「誰かが本当に求めているもの」へ
アイデアは基本的に“自分発”です。
自分が困った、自分が欲しい、自分ならこうする。
けれど、事業は“他人発”で動きます。
買うのは他人。
お金を払うのも、時間を使うのも他人。
つまり、アイデアを事業に変えるというのは、
「自分のひらめきを、誰かの“欲しい”に変える作業」
なのです。
アイデアの段階では気づかない「抜け」がある
たとえば、あなたが「勉強が続くアプリ」を考えたとします。
・勉強した時間を記録できる
・好きなキャラが応援してくれる
・SNSで成果をシェアできる
……すばらしい。でも、それがなぜ今、必要なのか?
誰が、どういう状況で、他の選択肢ではなく、それを選ぶのか?
ここが曖昧なままでは、“面白そう”で止まってしまいます。
「事業」にするには、“問い直し”が必要
ここで必要なのが、「誰の、どんな課題を、どう解決するのか?」という問い直しです。
これをしっかり掘ると、次のように変わります。
・ターゲットは「独学で資格を目指している社会人」
・夜の学習習慣を作るのが苦手
・継続できない理由は、“成果が見えづらくて、孤独になるから”
その上で、
・記録機能だけでなく、「次の予定を予約できる」
・キャラではなく「他の学習者と進捗を共有」
・SNSよりも「アプリ内の小さなコミュニティで支え合う」方が合っている
……と、同じアイデアでも「他人の生活の中で、自然に使ってもらえる形」に変わっていきます。
「通用する事業」には、数字・構造・継続性がある
事業として成立させるには、さらに以下の要素が必要です。
・お金の流れ(収益モデル)が成立しているか
・必要な人に、ちゃんと届く導線があるか(販売チャネルや広告)
・一度使って終わりにならず、繰り返し使いたくなる理由があるか
このあたりを「見える化」し、「数字」で語れるようになると、“通用する事業”として説得力が一気に増します。
あなたのアイデアは、磨かれていますか?
・誰が使う?
・どんな場面で?
・他の選択肢ではダメな理由は?
・どうやって継続してもらう?
・その人に、どう届ける?
これらの問いにすべて答えられるようになったとき、
あなたのアイデアは、夢ではなく“事業”に変わります。
そして『Real The Value』のような場に立ったとき、
ただの思いつきではなく、
「誰かの暮らしを変える価値」
として、REALと評価されるでしょう。
“プロの質問力”を盗め!事業ヒアリングでわかる5つの論点
――ゲストが語り出す前に、MCはすでに本質を見ている。
『Real The Value』を見ていると、
こんな瞬間に気づくことがあります。
ゲストがプレゼンを始める前、
チェアマンたちは真剣に資料を見つめ、静かに何かを考えている。
プレゼンが終わったときには、
鋭いツッコミや核心を突く質問がすぐに飛んでくる。
あの短時間で、彼らは何を見抜いているのか?
実は、事業を聞くときに“自然とチェックしている”視点がいくつもあります。
今回は、それを5つの論点として解説します。
1.「誰が困っていて、何に困っているのか」
最も基本であり、最もズレやすい論点です。
MCたちはこう見ています。
「これは“課題”としてリアルか?」
「本当にその人の生活に差し込めるのか?」
自分が感じた不便さをそのまま“市場のニーズ”
と考えてしまう人が多いですが、
ビジネスとして問われるのは、
「自分以外の誰かが、それを“お金を払ってでも解決したい”と思っているか」です。
2.「誰と比べて、何が優れているのか」
いわゆる“差別化”の視点です。
同じジャンルにすでにサービスや商品が存在する場合、
MCは
「それとどう違うのか?」
を最初に確認しています。
“優れている”というのは、スペックだけではありません。
価格が手頃、導入が簡単、デザインが好き、ストーリーに共感できる――
あらゆる面での「選ばれる理由」があるかが問われています。
3.「買わせる仕組みは設計されているか」
アイデアが素晴らしくても、届かなければ意味がありません。
MCたちは、
「どうやって見込み客に知ってもらうのか」
「どうやって購買まで導くのか」
を確認しています。
販売チャネル、広告戦略、SNS活用、インフルエンサー、リアル店舗……
買うまでの導線が論理的に組まれているかどうかは、
事業の根幹を左右します。
これが曖昧だと、「熱意だけ」「アイデアだけ」で止まってしまいます。
4.「一度売って終わりにならない仕組みがあるか」
単発で終わる事業は、事業ではなく“商品”です。
MCたちが注目しているのは、いかにしてユーザーと“関係性”を築き、継続的に価値を届けられるか。
定期購入、サブスクリプション、コミュニティ、体験コンテンツ、アフターサービス――
その仕組みがあるかないかで、評価は大きく変わります。
ここではLTV(顧客生涯価値)や継続率といった指標が鍵になります。
5.「この人に任せて、結果が出るか」
最後は、事業そのものではなく、“人”の話です。
MCたちは、プレゼンを聞きながら
「この人は途中で投げ出さないか?」
「冷静に改善できるか?」
「仲間を巻き込めるか?」
という視点で見ています。
言い換えれば、プロの目はこう問うています。
「この人は、“経営者”か?」
アイデアの良し悪しではなく、行動力・修正力・覚悟を見ているのです。
事業の中身よりも、
語るその姿勢が「REAL」か「FAKE」かを決める場面も少なくありません。
これら5つの論点は、『Real The Value』の場だけでなく、
あなたがプレゼンをするとき、
事業相談を受けるとき、仲間に話すとき――
あらゆるビジネスシーンで通用する“評価の眼差し”です。
自分の事業を、この5つの問いで見直してみてください。
「面白いアイデア」は、ここから「通用する事業」に変わります。
失敗事例から学べ!価値を見誤ったビジネスの共通点
――ありがちな落とし穴は?『Real The Value』流、
しくじり回避の目の付け所
ビジネスには、最初からうまくいくものなどほとんどありません。
でも、
“うまくいかない理由”には、
驚くほどよく似たパターンが存在します。
『Real The Value』で多くの挑戦者がプレゼンし、
チェアマンたちが首をかしげる瞬間。
そこには「本人だけが気づいていない共通のズレ」があります。
ここでは、ありがちな失敗の共通点を5つ紹介しながら、それぞれの“回避の視点”を解説していきます。
1. 「自分が欲しい」=「他人も欲しい」と思い込んでいる
これは最も多い失敗です。
自分が不便だったから、
自分が感動したから、
「きっと他の人にもウケるはず」
と思って事業化。
でも、MCたちはこう見ます。
「それ、あなただけが困ってたんじゃない?」
「他の人は、もう解決済みじゃない?」
どんなにアイデアが良くても、
それが“他人にとっての価値”に転換されていなければ、売れません。
回避のコツ:
ユーザーインタビューやアンケートで、“市場の声”を聞く癖をつけること。
2. 競合を調べていない、または「うちは違う」と思い込んでいる
「似たサービスはあります。でも、うちは想いが違うんです!」
――その言葉が、逆に“戦略がない”ことを露呈してしまう場合もあります。
競合がいるのは悪いことではありません。
むしろ、市場がある証拠。問題は、“どう差別化するか”です。
チェアマンたちはこう見ています。
「価格?スピード?世界観?」
「選ばれる理由が言語化できてるか?」
回避のコツ:競合の強み・弱みを書き出し、自分のポジションを“数字”か“行動”で明確に差別化すること。
3. 売り方・届け方を考えていない
意外と多いのが、
「商品はいいのに、どう届けるかがふわっとしている」
という失敗です。
「SNSで発信します」
「インフルエンサーに頼みます」
では説得力がありません。
チェアマンたちは、
プレゼンを聞きながら
「誰に」「どの媒体で」「どうアプローチして」「何%が買うか」
を無意識に計算しています。
回避のコツ:売れる流れ(集客→接点→購買)のシナリオを言語化してみること。
4. 「一回売って終わり」の設計になっている
一発売れても、次が続かなければ、それは“打ち上げ花火”です。
事業として見られるのは、「継続性」があるかどうか。
『Real The Value』では
「LTVは?」「継続率は?」「ファン化できる設計は?」
という問いが毎回飛び出します。
継続する仕組みがなければ、
いずれ顧客も離れ、
広告費だけがかかり続ける構造になってしまいます。
回避のコツ:サブスク・リピート・コミュニティなど、何度も接点が生まれる仕掛けを初期から計画しておくこと。
5. プレゼンの熱量が“理屈”に負けている
本人は真剣に語っている。
けれど、事業として冷静に見たときに
“根拠が弱い”
“感情に寄りすぎ”
と判断されてしまうケースです。
チェアマンたちは、熱量があるかどうかはもちろん見ています。
でも同時に、
「計画は?収支は?数字は?」
という冷静な目も忘れていません。
「熱」だけで進んでも、「軸」がなければ崩れます。
逆に、「理屈」だけでも、「共感」がなければ広がりません。
回避のコツ:“熱意×戦略”で、どちらも言語化できるように練習すること。
失敗とは、落ちることではありません。
“ズレに気づかず走り続けること”こそが、最大のしくじりです。
だからこそ、
『Real The Value』
のようなフィードバック型の番組は価値があるのです。
自分の事業を、定期的に“疑って、問い直す”。
それが、失敗を防ぎ、未来のREALをつくる最短ルートです。
アイデアを“スケール”させるロードマップの描き方
――PMFからMVP、そしてEXITへ。
事業を段階的にバリューアップするプロセスとは
「このアイデア、すごく面白いと思うんです」
「将来的には、月商1億を目指したい」
「いずれは売却やIPOも…!」
こう語る挑戦者は多いものの、
それを聞いたチェアマンたちが返すのは、たいていこうです。
「そのスケール、どうやって実現するの?」
「今はどのフェーズにいるの?」
つまり、“スケールしたい”だけでは足りません。
「どこにいて、どこへ行こうとしているのか」を段階的に描ける人こそが、事業を現実に変える力を持っています。
その指標になるのが、PMF、MVP、EXITというフェーズです。
第一段階:PMF(プロダクト・マーケット・フィット)
PMFとは、
「市場が本当に求めているもの」と
「自分のプロダクト」が噛み合っている状態のこと。
簡単に言えば、
「このサービス、ほしかったんだよ!」
とユーザーに言われる段階です。
この段階でやるべきことは、“完成度”ではなく、“仮説検証”。
-
誰がどんな課題を抱えていて
-
それをなぜ他ではなく自分のサービスで解決するのか
-
それをどうやって知ってもらい、買ってもらうのか
この仮説が現実に合っているかを、ユーザーの声で確かめていきます。
重要なのは、正解を出すことではなく、間違いを修正できる仕組みにいること。
第二段階:MVP(Minimum Viable Product)
MVPとは、「最小限の機能で価値を検証できるプロダクト」のことです。
PMFが見え始めたら、今度は「形にして試す」ステップです。
ここで求められるのは、“完璧”ではなく“早さ”。
まず最低限の形を作ってリリースし、
リアルな反応を見ることで、
開発リスクや市場ズレを回避します。
たとえば…
-
高機能のアプリではなく、LINEで手動対応
-
自社開発ECサイトではなく、SUZURIやSTORESで販売
-
本格広告ではなく、X(旧Twitter)やInstagramで投稿して反応を見る
「売れるかどうか」よりも、「反応する人がいるか」を見極めることがポイントです。
第三段階:事業化・スケーリング
PMFとMVPでニーズと反応が見えたら、次は「事業としての構造を整える段階」です。
ここでやるべきことは以下のような内容です。
-
CAC(顧客獲得コスト)とLTV(顧客生涯価値)のバランスを取る
-
販売チャネルを安定させる(SNS/EC/リアル店舗など)
-
スタッフや業務の仕組みを整える(委託・マニュアル化など)
この段階では、「売上をどう作るか」だけでなく、
「それをどう支え続けるか」という構造への視点が求められます。
最終段階:EXIT(出口戦略)
EXITとは、
「事業の出口=どう終えるか、手放すか、次のフェーズに移すか」
という視点です。
-
M&A(事業売却):他社に買収されて、自分は次の挑戦へ
-
IPO(株式上場):市場に公開して資金を集め、より大きな成長を目指す
-
継続的運営:自身で保有し続け、収益事業として育てていく
多くの人が“始め方”ばかりに注目しますが、
“どう終わるか”を考えておくことが、事業設計の質を上げます。
最初からEXITを考えることで、
経営の意思決定がブレなくなり、
パートナーや投資家にも信頼されやすくなります。
スケールさせる人は、「今どこにいるか」が言える人
「スケールしたい」と言う前に、
・PMFは取れているか?(ユーザーに喜ばれているか)
・MVPは試したか?(実際に価値を届けてみたか)
・CACとLTVの構造は崩れていないか?(採算は取れているか)
・どのEXITを目指しているか?(次の一手が明確か)
この4点が語れる人は、実現可能なビジネスを描いている人です。
スケールは夢ではありません。
段階的に積み上げ、数字と構造で裏付けされた“プロセス”です。
それがあるからこそ、アイデアは“現実の価値”に変わります。
『Real The Value』でREALを勝ち取る人たちは、
必ずこの階段を一歩ずつ上がっているのです。
この視点があれば、あなたも“価値を見抜く人”になれる
――番組を100倍楽しむための
「視聴者からビジネス解読者」へのステップアップ講座!
『Real The Value』を見ていて、こんなふうに感じたことはないでしょうか?
「なんであのアイデアはREALで、こっちはFAKEなの?」
「自分だったら、どこに注目して評価するんだろう?」
もしあなたがそう思ったなら、すでに“ただの視聴者”ではありません。
あなたは今、「価値を見抜く目」を養おうとしているところです。
この目線は、
ビジネスを始めたい人にとっても、
すでに動き出している人にとっても、
一生使える“武器”になります。
ここで、これまでの内容を踏まえて
『Real The Value』を“ただ見る番組”から“学びの場”に変えるための
視点を3つにまとめてお伝えします。
1. 「話の奥にある“数字”を読み取る」
出演者のプレゼンには、実は多くのヒントが散りばめられています。
売上、粗利、LTV、CAC、継続率、リピート率…
チェアマンたちは、
話を聞きながら
「この構造、利益出るのか?」
「再現性あるか?」
を頭の中で瞬時にシミュレーションしています。
あなたも、
「この事業モデル、LTVとCACのバランスはどうだろう?」
と仮説を立てながら見るだけで、理解度は一気に深まります。
2. 「熱量だけでなく、“構造”に注目する」
番組では、「想いが強い=REAL」とは限りません。
むしろチェアマンたちは、
その熱意が“誰のために、
どんな形で、
どう続くのか”という構造になっているかを見ています。
アイデアがあっても、
「売り方」「届け方」「継続の仕組み」
が設計されていなければ、評価は得られません。
「この人のビジネス、どこまで再現できて、どこまで伸ばせるんだろう?」
この視点が持てるようになると、
どんな事業でも“中身”が見えるようになります。
3. 「評価の言葉に、“自分への問い”を重ねる」
チェアマンたちのREAL/FAKEの判断には、
彼らの事業経験や失敗の哲学がにじんでいます。
「自分の事業だったら、この質問に答えられるか?」
「私のビジネスは、NPSで評価できる? LTVは出せている?」
「EXITは描けている?」
番組を通して、他人の事業を学びながら、自分を問い直す。
それができたとき、あなたは“価値を見抜く側”になっているはずです。
最後に:視点が変われば、世界が変わる
今、事業をしていなくてもいい。
何かを始めようとしている途中でもいい。
“見る目”を持つことで、
あなたの中に眠っていたアイデアは、
「通用するビジネス」に育っていきます。
『Real The Value』は、ただのバラエティでも、
ビジネス番組でもありません。
それは、「価値の本質を問う場」であり、
「自分の未来をリアルに描くきっかけ」になりうる場所です。
この視点を手に入れたあなたなら、
次にREALを引き当てるのは――
きっと、あなた自身です。
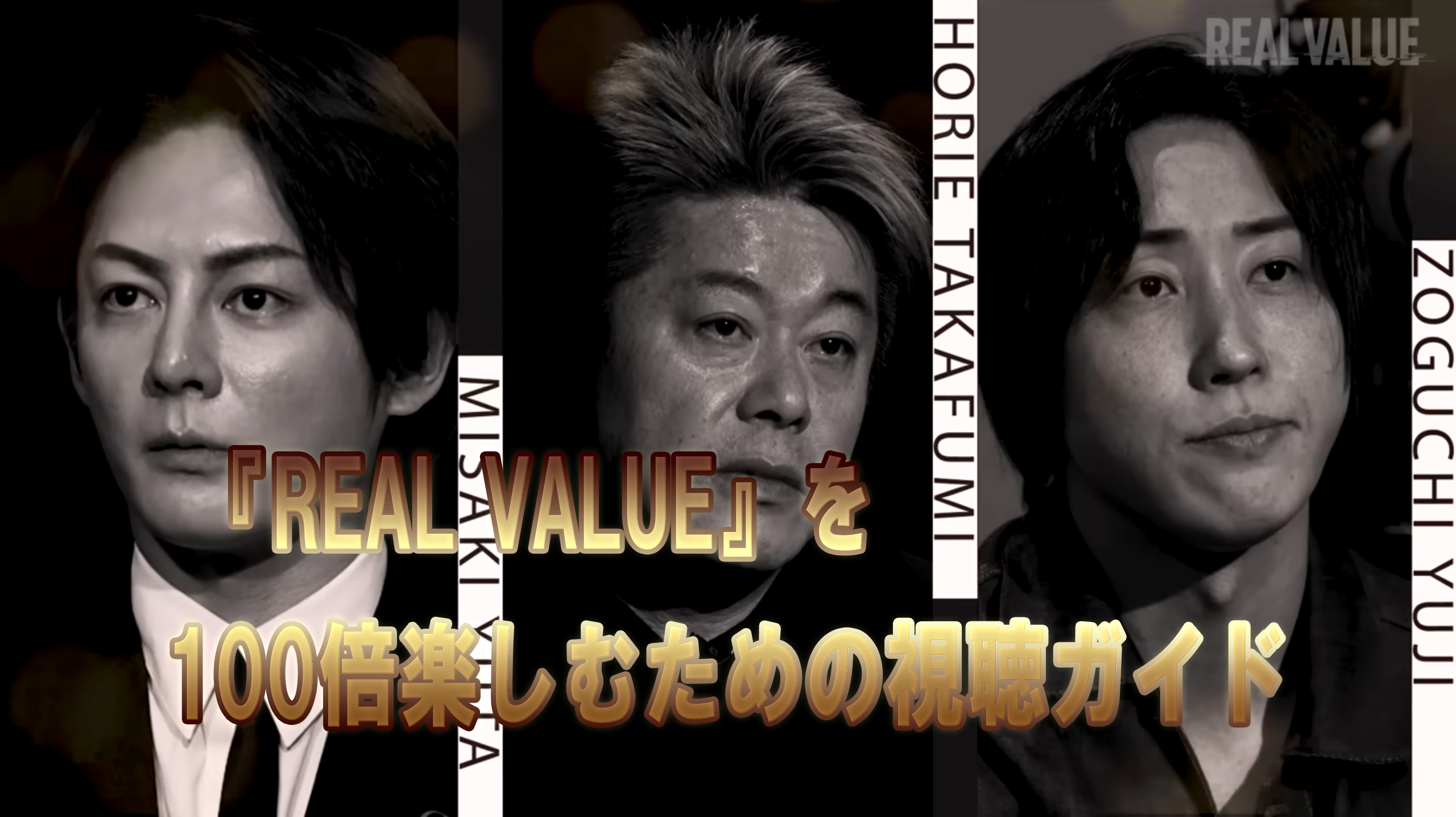
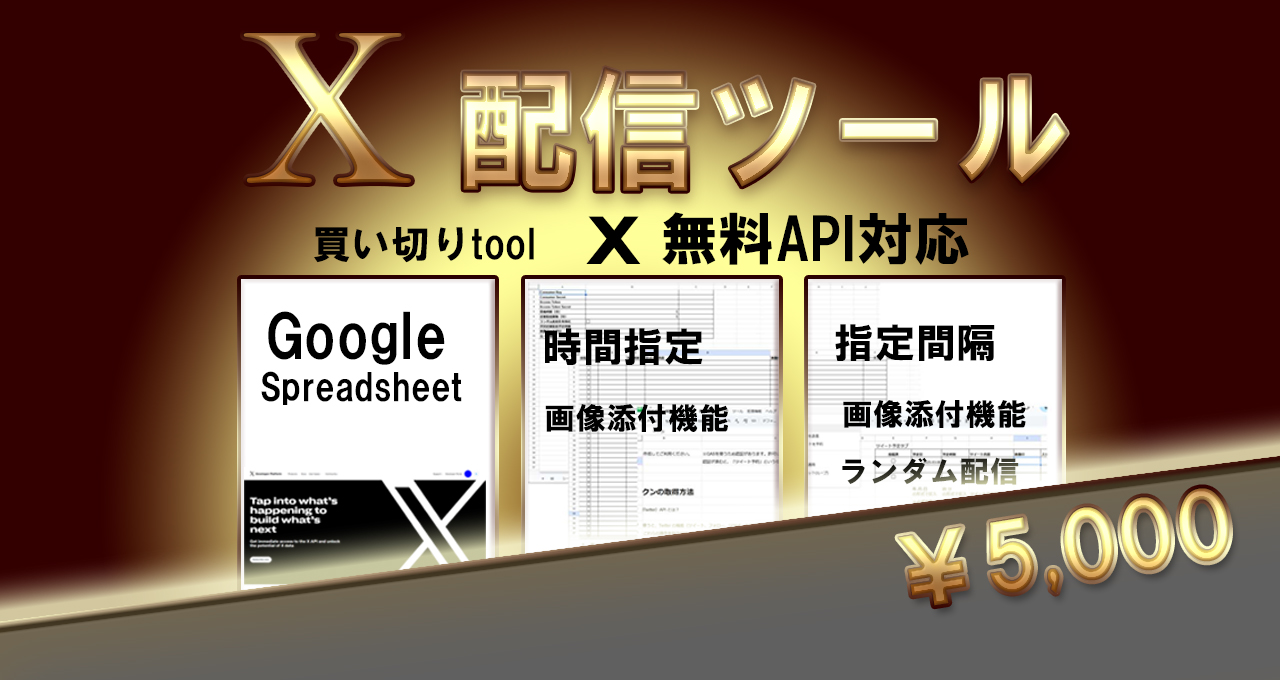

コメント